

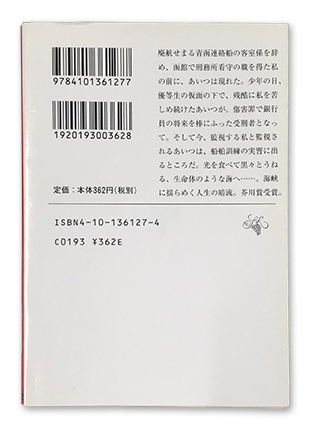
案内文02
「もしどこかでもう一度」編集者・鈴木朝子
『海峡の光』辻 仁成
どこかでもう一度会ったらどんな顔をすればいいんだろう。
振り返ってそんなふうに思う出会いはいくつかある。とくに憶えているのは10代のときの記憶で、なんとなく気が合う友達がクラスにいて、一緒に行動することはほとんどなかったけれどたまにふたりでいろんな話をする時間があった。
その友達が退学することになったと教えてくれたのは誰だったのか、すでに違うクラスにいた友達の退学のニュースを知っている人は周りには少なかったし、実際あまり表沙汰にならなかったのだと思う。教えてくれた誰かの沈痛な表情はなんとなく記憶に残っていて、退学の理由は幸せなものではなかったはずだった。
なにかの用事で友達の住んでいた町の駅で帰り道に途中下車したある日、駅の階段で退学後の友達とばったり会った。私服姿で、目が合っても笑わなかった。近づいていったら目元だけ少し和らげて「ひさしぶり」と言ってくれて、名前を呼んで話しかけようとした私をさりげなく遮って「元気だった? またね」と言って足速に去っていった。
気づかないふりをしてすれ違えばよかったのかもしれないな、といまでも思う。
また電車に乗って、友達の身に振りかかったのかもしれないさまざまな出来事を想像した。どれも幸せなものではなくて、軽はずみに声をかけた自分をいまいましく思った。再会が片方にとってはただただ嬉しいものでもう片方にとってはそうではない、ということがあるのだと知った。
そして、いつか友達にもう一度ばったり会うことがあったら私はどんな顔をして会えばいいのだろうと考えた。なにも知らないまま会えなくなったあとのこちらだけが無邪気な最初の再会ではなく、再々会がもしあったら。
「どんな顔をして会えばいいんだろう」と、『海峡の光』の主人公とかつていじめっこだった同級生のどちらがより強く思ったのだろう。主人公が刑務官として働く函館の少年刑務所に、傷害罪で東京の刑務所に収監されていた昔の同級生が移送されてくる。
ふたりの立場は逆転しているはずだった。いじめられっこだった過去に別れを告げるように体を鍛え、ラグビーに打ち込んできた主人公は、同級生に対してもう怯える必要はなかった。そして同級生にとって、自身を更正へと導く立場にある主人公は脅威であるはずだった。刑務官と受刑者として再会したふたりの逆転した立場は、ふたりの心のなかでは果たして……
再会したとき、ふたりは表面的には初対面の顔をした。物語は主人公の視点で展開するから主人公が相手を認識していることが読者にわかるけれど、受刑者になった同級生が気づいているかどうか、示唆されるもののラストまで明かされることはない。だから読み進めながら、同級生の存在に終始心を振り回されることになる。振り回されながら、一度築かれた人と人の関係は変わらないと自分が信じ込んでいることに気づく。その心の枷のようなものに、しばし呆然とすることになる。
あらすじ/『海峡の光』辻 仁成
北海道・函館で刑務所の看守を務める主人公。ある日、少年時代に彼を陰湿にいじめていた同級生・花井が、傷害罪の受刑者として現れた。花井は模範囚として過ごしていたものの、仮釈放が決まると問題を起こして自ら取り消しにする。主人公は、同級生だったことを気づかれるのではないかと内心で怯えながら過ごす。そしてふたりは船舶訓練の監視者と被監視者として海に乗り出た。第116回下半期芥川賞受賞作品。
案内者プロフィール
鈴木朝子。1977年千葉県生まれ。編集者。株式会社アピックス勤務。ふだんは企業・学校の広報媒体(コンセプトブック、ブランドブック、社史など)のライティング・編集に携わる。選書の仕事としては高校生に向けた「はじめの1冊×100」「将来をかんがえる10冊」など。当サイト主宰。

書籍情報
『海峡の光』(1997年新潮社より発刊)。
現在、新潮文庫より発売中。
