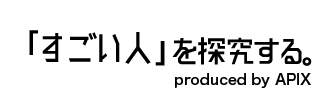米澤敬さんの著作『信じてみたい 幸せを招く世界のしるし』は、世界中の言い伝えを集め、見開き2ページで優しい挿絵と短文の解説とともに紹介する本である。いわゆる“癒し系”にも思えるこの本の著者まえがきは、こう始まる。
「サインは、『きざし』や『しるし』をあらわします。デコード(decode)がコード、すなわち暗号を解読することを意味するように、デザイン(design)はもともと『きざし』を解読する、あるいはかたちにすることでした。」
米澤さんは、1970年代~1980年代前半にかけて名をはせた雑誌『遊』や、『ライプニッツ著作集』をはじめとする哲学・思想系の単行本で著名な出版社・㈱工作舎の第3代編集長。『遊』は文章とデザインを融合させたスタイルで、朝日出版社の『エピステーメー』1とともに、“難しくてよくわからないけれどスゴい”雑誌の双璧だった。
『信じてみたい…』の本の造りと、いきなり語源から始まるまえがき、巻末に付された膨大な参考文献には、対象読者層こそ異なっても、米澤さんが守る工作舎の香りが漂う。
図鑑少年とアートの道断念
米澤さんは1955(昭和30)年、群馬県前橋市に生まれた。
自らが「編集」について語った『編集舞ぃ舞ぃ』の冒頭には、最初に買ってもらった本の記憶として小学館の『魚介の図鑑』、次いで幼なじみの兄から借りた『たのしい四年生』付録「ものしり世界一日本一」の話が記されている。「小学校低学年時代は、ほとんど図鑑を眺め暮らしていたようなものである」ともあり、図鑑づくりを思い立って挫折した話で終わる。
「子どもの時から読むより見るほうが……『少年マガジン』の特集、大伴昌司2が手がけていた『ミッドウェー海戦 なぜ負けた』とか、そういう図解グラビアが好きだった」
この生来の“図解”好きに、小学校時代、教師から「新聞委員をやれ」と言われて壁新聞やガリ版刷りの新聞をつくったことで、作り手としての楽しみが加わる。
「新聞委員は僕ともう一人で、どっちも学級委員にはならない、なれないタイプ。先生も不思議な人で、僕が生き物好きだったのを知って、水産試験場とかに連れて行ってくれたりした」(米澤さん、以下同)
これも編集を担当した小学校の卒業文集に米澤さんが書いた将来の夢は、石森章太郎3が好きだったことから「マンガ家になりたい」――中学に入るとこれがイラストレーターに変わった。
「横尾忠則さんが出てきて、少年マガジンの表紙まで手がけていた4。すごいなと思って」
こうしたアートへの志向は、中学の友人によって転機を迎える。
「この友達はすごかった。初見でピアノ弾くし、フルートでは全国大会で準優勝するくらい。中学に入った時にシンフォニーを書いていて、後に群馬交響楽団が演奏したレベルだった。彼とはフォークバンドをやったんだけど、自分でスコアを書いてきて、コーラスとか細かいところまでめちゃくちゃに文句を言われる。こっちは『楽器弾きながらは無理だよ…』って弱々しく。なのに、彼が小学校の卒業文集に書いてた夢は『県の職員になりたい』(笑)」
絵を描くにしても、これくらいでないと圧倒的にはなれないんだろう、自分はムリだと、米澤少年は何となくアートの道をあきらめたのだという。
「イラストレーターは到底無理だから、デザイナーになりたいと。横尾さんはアートとデザイン、絵画の混じった微妙なスタンスにいると思うけれど、デザインだったらと。自分は影響されやすく、飽きやすくて関心の対象がコロコロ変わるのは自覚している(笑)」
とはいえ、今も米澤敬さんは年1回、自らが属するバンド・PICABIA(ピカビア)のライブに立つ。ブックデザイナー2人と組んだこのバンドで、ビートルズやレッド・ツェッペリンなど10数曲を演奏し、メインボーカルを務める。粗削りで苦しいところもあるが、野太いシャウトには力がある。たぶん、編集ではなくダイレクトで“声を出すこと”への想いには、まだ飽きが来ていない。

雑誌『遊』の衝撃で工作舎へ
大学卒業の直前に電話して「就職させて欲しい」と頼み、十川治江5・現社長から「ムリだけど、一度遊びに来なさい」と言われたのが、米澤さんと工作舎の馴れ初めである。
「東京厚生年金会館の近くの事務所を訪ねた時に、たまたま松岡(正剛)6さんが来て、会議をやることに。『隅で座って聞いてていいですか』といったら『いいよ』っていうから、話を聞いていた」
理学部鉱物学専攻だった米澤さんが、工作舎に入社希望の電話をかけたのは、図鑑から絵描き、さらにデザインとつながってきた「好きなもの」のひとつの先端を、工作舎の雑誌『遊』に見たからだった。米澤さんが『遊』に接したのは高校時代。松岡正剛氏ら、後に工作舎を創立するメンバーが1971(昭和46)年9月に発刊した。“オブジェ・マガジン”を謳い、毎号定められたテーマに関する文章や写真、図版が詰め込まれ、杉浦康平氏7の圧倒的なデザインで読者にさまざまなイメージを喚起する8。
「創刊号をみて、その時はデザインというより存在感がすごかった。ほとんど読めず、立ち見でパラパラ見ただけだけど」
この第一撃の後、米澤さんは大学に入ってデザイン研究会に入部し、杉浦康平好きの先輩から『遊』第Ⅰ期の一冊を見せられて決定打を受ける。デザインをやりたいという希望が膨らみ、鉱物学専攻としての就職活動をせず、自らミニコミ誌を発刊する目標を立てた。そのための修業も含めて、工作舎にアプローチしたのだった。
「当時は『遊』第Ⅱ期が始まるところで、会議では、PRを兼ねた0号としてポスターマガジンをまずつくろう、という話をしてました。だけどそれが出ないまま、『遊』の第Ⅱ期の第1号が出ちゃったんで、これは作る気ないな、と思って、電話して許可もらってつくったのがこれです。今見るとどうしようもないけど」
飯場でアルバイトして10万円近い制作費を捻出、初編集・初デザインとなるポスターマガジンは、札幌の書店2か所が置いてくれた。しかし、定価300円で売れたのは数部。別に意気阻喪はしなかったが、先行きのめどは立たなかった。

上京して工作舎の書店営業に
こうしたなか、自主制作に加えて何度か工作舎に足を運んでいた縁で、米澤さんは、松岡編集長の依頼で『遊』の「ローカスフォーカス」(地方の文化状況レポート)を書き、工作舎の編集者向け勉強会「遊塾」も受講することになる。「遊塾」は週1回、業務終了後に同社で深夜まで行われ、開催期間は半年、20回を超える予定が組まれていた。
「札幌から通うわけにもいかず、どうしようかと。京都から出てきた後藤繁雄9もウロウロしていて、そしたら当時の工作舎の営業の人が書店営業手伝ってくれたら歩合で給料だすから――と。『遊軍』っていってましたが、昼食代が1日500円、生活費として月5,000円という待遇、大卒初任給が10万円くらいの時代です。後藤は持ち前の営業力でどんどん注文をとった。今では考えられないようなケンカ腰の交渉で100冊とか200冊の注文をとってくる。僕も頑張ってとったんだけれど、結局、売れずに返品されてくるから、歩合給はウヤムヤ(笑)」
書店営業のほかに、元々やりたかったデザインの手伝いもした。
「ただあまりに食えないので、デザイナーさんに相談したら、『じゃあバイトしたら』と事もなげに。おいちょっと待て、朝から営業して帰って伝票処理して、デザイナーの手伝いが夜8時くらいから深夜1時とか2時まで。いつバイトするんですか、という感じ。同じような境遇の10人くらいでパンの耳を買ってきて、朝と夜、フライパンで温めてマヨネーズをちょっとつけて食べるような生活でした」
超ブラックの生活ながら、札幌に戻ってミニコミ誌発刊を考えていた米澤さんにとっては、雑誌を“売ること”のシビアさ、出版業界のシステムや書店の現場が実地体験でき、デザインのOJTでも鍛えられた1年間(「遊塾」が長引いたため)は得難い経験となった。
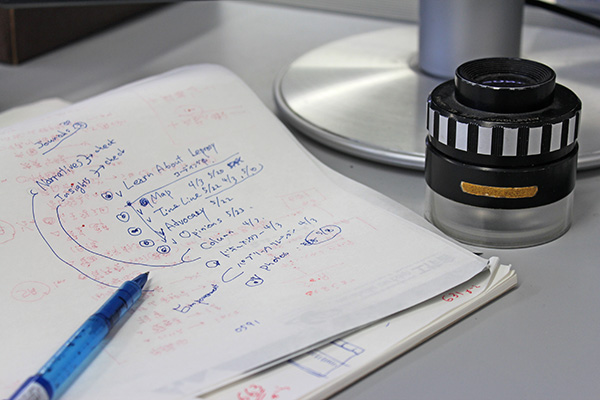
第Ⅲ期『遊』の中心メンバーへ
「遊塾」の終了直前、米澤さんは松岡正剛編集長から「工作舎で働かないか」と誘われる。
「創立メンバーの松岡正剛、高橋秀元10、十川治江はヒーローで、一緒にやらないかと言われるのは、ビートルズにメンバーにならないかと言われたようなものだった。正式のアルバイトも、永田町駅の長いエスカレーターに乗ってる間に寝たとか、女性スタッフがママレモン(ライオンの食器洗剤)で頭洗ったとか逸話があるように超ブラック勤務だったけれど、労働とは違うところで仕事していた。今はもちろんやっちゃいけないですけど」
基本給は「遊軍」時代の月5,000円から3万円になったものの、大卒初任給の3分の1以下、「それまでの生活が生活だから結構いける(笑)」と思えたのは、より過酷な飯場も経験した米澤さんの若さと、工作舎の仕事がもつ身過ぎ世過ぎとは違う何かだった。
松岡編集長が米澤さんに声をかけたのは、遊塾の若手メンバーから3人をセレクトして3チームを編成し、月刊となる第Ⅲ期の「遊」をつくる――という構想からだった。
「第Ⅰ期の『遊』は不定期、第Ⅱ期は隔月でした。これは後から聞いた話なんですが、雑誌の広告営業をすると『月刊じゃないとダメ』と言われる。それは条件じゃなくて、単に断る口実なんだけれど、当時の経営陣はまともに受け取ってしまった(笑)」
選ばれたのは、米澤さんと後藤繁雄さん、元シティロード編集者の宮野尾允晴さんの3人。この段階から、米澤さんは「編集」を中心に活動していくことになる。
「『遊軍』時代、デザイナーを手伝っていて『杉浦康平を超えなさい』と。無茶なこと言うなとは思ったけれど、やりたがりだから凝ったことをやろうとする。当時DTPはまだなくて版下作業なので、器用なほうじゃないから、写植貼って文字詰めて、別版をトレーシングペーパーに、みたいな感じにしていくと版下がゴテゴテに。で、『米澤の版下は汚いから編集に行け』と(苦笑)」
とはいえ特集はやれるし、月刊化で広告も入る、これから豊かになる――と聞かされ、勇んで仕事に打ち込んだ。

軋む工作舎の中で
しかし、1980年の第Ⅲ期『遊』発刊後、工作舎はいろいろと軋み始める。
「僕ら3人は気づいてませんでしたが、他の遊塾メンバーから結構嫉妬されていた。『なんであいつらが編集で俺らは営業や受注仕事なのか、俺らが稼いであいつらが金使って』的な、ギスギス感が出てきてしまった。もともと、松岡さんが『遊塾』を始めたころにも、古いメンバーが結構辞めている。『遊』は赤字雑誌なので、創刊当初から受注仕事で稼いで穴埋めしていました。そういう堅実な仕事のできるプロフェッショナルが結構辞めていて、さらに『遊塾』メンバーにも軋みが出て」
創立から工作舎の事業は、『遊』など自社出版物と、「プロジェクト」と社内で呼ばれる受注出版物(会社案内・PR誌・年史等の企業・団体関連もの)の二本立てで、会社経営的には後者に依存するところが大きかった。
第Ⅲ期『遊』も売れ行きは芳しくなく、さらに内容もブレ気味だったという。
「『遊』って、わかる人だけわかればいい、売れなくても良いものをつくればいいっていう姿勢で、実際に第Ⅱ期までは、レベルは落とさない、杉浦さんのデザインで歴史に残る本をつくっているとの自負も矜持ももっていたと思う。ところが第Ⅲ期は、“広告と販売で雑誌として自立させる”という松岡編集長の意向もあって、大衆路線で割と媚びた感じがする。評価すべきところもあるけれど、今からみると第Ⅲ期は、読者ニーズを吸い上げて期待に応えるものをつくっているんでもないし、かといって自分たちのやりたいことを徹底的にやっているんでもない、中途半端で一番良くないかたちになっていた」
米澤さんは、この路線に疑問をもったこともあったが、松岡編集長はカリスマ的存在で、何かが変わるだろうと思ってやっていくしかなかった。
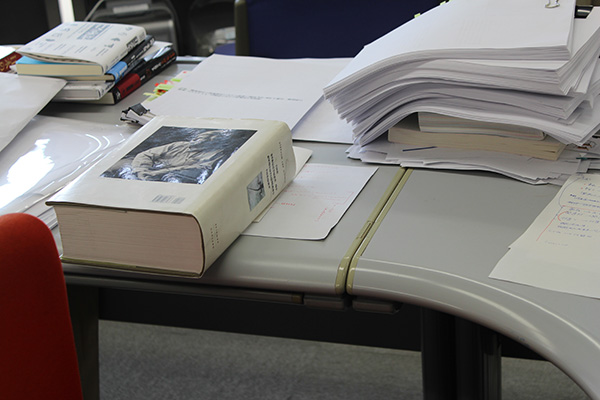
カリスマが去った後
『遊』の月刊化で、隔月刊時代の倍のペースで赤字は膨らんでいく。そんなある日曜日、米澤さんが一人で仕事していると、松岡編集長が肩をたたいて、「米澤君、工作舎なくなるかもしれないよ」と告げた。当時、工作舎の借り入れは体力の限界を超えつつあり、結局、大手印刷会社と教育教材会社から資金提供を受けて乗り切ることになる。その結果、1982年に松岡編集長は工作舎を離れ、有力な編集者も何人か辞めていくこととなった。
現在の十川社長が第2代編集長となり、残った米澤さんらは経営再建に邁進する。1980年代後半のバブル景気が幸いした。
「よくもったな、と思います。バブルがあったのは運がよかった。会社案内5本並行とか、ものすごい量をやりました。もうひとつは、『生命潮流』(ライアル・ワトソン著)などのニューサイエンス。僕は好きではなかったけれど、1960年代のヒッピー文化の影響を受けた科学と宗教、古典的思想を結び付けて新しい見方を提示する本が流行って売れ、会社は持ち直した」
米澤さんが出版編集の難しさ、そして組織とお金の現実に直面した10年間だった。


第3代編集長で2度目の再建を担う
2000年前後、現在の中上千里夫会長が社長を退き、松岡氏の後を務めていた十川第2代編集長が社長になったのに伴い、米澤さんは新編集長への就任を打診された。
「『米澤君、編集長になればつくりたいような路線を敷けるから』『給料も増えるから』と言われて。だけど、経理の書類をみたら、バブル崩壊後にまた借金がたまっている。デジタルメディアの伸長もあり、紙媒体としての会社案内の新作中止やPR誌の打ち切りが相次いで。編集長になったとたんに明かされて、給料は上がるどころか下がった。さらに『自社出版を当分やめるから』と。何のために編集長になったんだか(笑)」
そうした中で米澤さんは、大黒柱の一人としてまたも大車輪で働き、大手マンションメーカーのPR誌の受注などを手がかりに、2度目の再建を成功させる。しかも、編集・デザインに加え文章も手がけるようになった。
「もともと文章と企画書を書くのは好きじゃなかったんだけど、文章はここ10年ほどプロジェクトで書く機会が増えて、面白くなってきた。企画書は相変わらず嫌いだけども」
一方で、工作舎の新たな編集長像も模索した。元々、打合せ等でも、大御所的な振る舞いはしない。大手企業との打合せもあるが、米澤さんは、基本的にTシャツにジャケット、Gパン、冬はこれにカーキのコート。こうしたスタイルも、米澤さんが初めて工作舎を訪れた時から、あまり変わっていない。会社が禁煙になれば、素直に下のコンビニエンスストアの喫煙場所まで下りてタバコを吸う。
「松岡さんがカリスマで、松岡=工作舎だった時と今は違う。カリスマがいれば、無理やストレスはある程度糊塗できるけれど、会社という組織がそれでOKというわけではない。今の工作舎は、カリスマ運営の破綻がトラウマとしてあるから、スローガンを立てて全社一丸はやらない、僕もそういう存在にならないようにしている。松岡さんとは器が違うとも思うし。松岡さんは“師匠”で、編集実務を教わったことはほとんどない。宇宙はこうとか、歴史はこうとか学びながら、実務は『遊』編集の手伝いしながら見て盗む、という職人みたいな育成法。カリスマがいたから成り立った方法で、むしろそれがよかったけれど、今はたぶん違う」

編集の両極をめざす自由さ
編集長となって20年近くを経た現在も、米澤さんが温めてきた企画の幾つかは凍結状態のままで、これから少しずつ実現させていくつもりだという。ただし、工作舎の出版物・制作物のカラーについては、意外なほど淡泊な見方をする。
「工作舎らしいね、と言われるが、それはメンバーの色。代々の刷り込みがあるからそうなっているかもしれないけれど、出版でもプロジェクトでも、工作舎らしくないからダメ、ということはない。なぜかといえば、プロジェクトはどんな相手でも基本はやらなければならないから。ごく稀に断ったケースもあるけれど、基本的には受ける。そういう仕事で鍛えられると、本当に好きなものをやる際にも相対化するように働く。結果的に工作舎のカラーはあるけれど、こうじゃなくてはならないというのはたぶんない」
こう言い切れるだけの歴史を、米澤さんは工作舎で重ねてきた。また、編集は定義できないし、最終的にはセンスだ、という持論もバックになっている。鍛えられるのは、最終的に読者をイメージすること、マスマーケティングと違って具体的な誰かがどう思うかを意識するだけ──と、編集長の米澤さんは言う。
一方で、編集者としての米澤さんの抱負は、こういうものだ。
「でもね、本音では何もしない本がいちばんすごいと思うところもある。編集者もデザイナーも何もしない素のままの本。そう言いつつ、翻訳ものや編集主導で創る本、昔でいうと『全宇宙誌』みたいな、著者がいなくて図版を集めて、ピクトリアルにまとめていく方向でももうちょっとやりたい。今はカメラマンの仕事が埋まらないから抱えられないけれど、昔は、編集もデザインもカメラマンもいて工作舎だったから」
いたずらっぽく話す姿には、自由な発想と工作舎を支えてきた歴史の双方が見える。