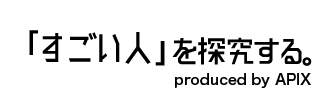「『人を喜ばせたい、人から喜ばれたい』という気持ちが強くて、そのためならばポジティブにいろいろと自分なりに工夫してみようと思える。ホスピタリティが問われる仕事には、そうした人が向いています」
ザ・リッツ・カールトン大阪1の副総支配人として、日本に初めてリッツ・カールトン式ホスピタリティを定着させた四方啓暉(しかたよしあき)さんはこう語る。四方さんはホテルマンとなった1969(昭和44)年から約42年間にわたって、ホテル界の第一線で活躍し、日本におけるホスピタリティの発展に貢献してきた。その後も、大学教授として、ホスピタリティの世界での活躍を夢見る後進たちの指導に尽力している。
まさにホスピタリティひと筋と言っても過言ではない四方さんの「ホスピタリティ人生」とは、どのように始まり、どのように育まれてきたのだろうか──。
ホスピタリティの原点
四方さんは終戦の翌年にあたる1946(昭和21)年2月、2人兄妹の長男として神戸で生まれた。姫路出身で神戸の商社に勤めていたお父様は、おしゃれでやさしく穏やかな人柄で、すべてにわたって四方さんを応援し続けた。生まれも育ちも神戸のお母様は、美人でかわいい性格の持ち主で、愛情に満ちた上品な振る舞いは四方さんに少なからぬ影響を与えている。
「両親の教育方針は厳しくありませんでした。子どもの頃、家の中にはいつもジャズやポップスの音楽が流れており、ポール・アンカの曲などもよく聴きました。父は日曜日になると、必ずと言っていいくらい、子どもたちをハイキングなど遊びに連れて行ってくれました。とても素敵な父でしたね」(四方啓暉さん)
四方さんのホスピタリティ人生の原点は、この幼少期から少年期に形成されたと言っていい。
「少し物心がついた頃、ぼくは自宅の近くにあったキリスト教系の幼稚園に入れてもらいました。戦後間もなくのことで、この幼稚園は進駐軍2の援助を受けて運営されていたようです。そうした環境のなかで、みんなで助け合うとか、キリスト教的な文化に自然と慣れ親しんでいきました。ぼく自身にとって、それはとても心地いい場所でした」
卒園後、四方さんは神戸市立小学校へ入学する。そこでは、戦争孤児3がクラスの仲間として入ってくる。
「自分が良かれと思ってやることが、相手に喜んでもらえる、といった意識が芽生えたのは、戦争孤児院(児童養護施設)から通う小松君という友だちとの交流がきっかけでした。彼はいまでいう発達障害を少し持っていました。クラスに来ても誰もかまわないから、ぼくが話しかけるわけです。横に座ってね。そうすると、とても喜んでくれるんです。クラスメイトたちも、ぼくらが手をつないでみんなの輪に加わろうとすれば、拒むことなく入れてくれました。誰かに手を差し伸べたり、声をかけたりすることは、ぼくにとっては特別なことではなかったし、周りからも『あいつええかっこしいしてるな』などと見られることもありませんでした」
四方さんは、両親ともにキリスト教信者ではなかったが、毎週末になると日曜学校4へ通った。クリスマスには聖書を読んで、キャロル(讃美歌)を謳ったり、キリスト誕生の物語を芝居で上演したりした。
「いろいろな人と出会える環境があって、そのなかで、どう考えて、どう立ち振る舞ったらいいかを、自然と教えられました。また、そのことがとても楽しかったですね。友だちのことを大事にしたり、キリスト教の考え方が心地いいと感じたりしたのは、いま振り返れば、ぼくのスタートだったのかな、と思います」

ホテルマンへの憧れ
四方さんが将来の職業について具体的に考えたのは、高校2年生の時、たまたま耳にした深夜ラジオがきっかけだった。
「ゲストに東京ヒルトンホテル5の副総支配人がいらしていて、ホテルマンになった理由について話をしていました。彼が言うには、『ホテルの総支配人6とは、街の経済や文化、交流の中心でなければいけない。また、困ったお客様がいればいろいろなお世話もする。ホテルマンというのは何でもできなければいけない。だからこそ、その地域でみんなから尊敬されるし、みんなが憧れるんだ』と。こうした話を聴いて、みんなから尊敬されて、やりがいのある職業というのは、ぼくが小学校以来やってきたことの延長線上にあるような気がしたんですね」
ホテルマンになることを心に決めた四方さんは、高校卒業後に立教大学へ進学する。当時、日本でホテルに関する専門的な勉強ができる唯一の大学が立教大学7であった。志望校への入学を果たした四方さんは、「ホテル観光講座」8を通じてホテルの基本や専門知識を学ぶ傍ら、実際に現場を経験するために一流ホテルでのアルバイトを始める。
「東京の帝国ホテル、ホテルオークラなどでアルバイトしながら、勉強させてもらいました。興味を持って先輩を訪ねて行くと、一生懸命に教えてくれて、悪い人は一人もいませんでした。誰かを訪ねれば大事にしてくれるんだ、といういい思いをしながら回ることができました。あれで嫌な先輩に会っていたら、こんな商売は嫌だと思っていたかもしれませんね」
一方で、幼少期にキリスト教の文化に触れた経験を持つ四方さんは、大学公認のYMCA(Young Men's Christian Association)クラブにも入部する。
「当時は学生運動が盛り上がった時期でしたが、ぼくには少し違和感がありました。そこで立教と言えばクリスチャンというわけで、キリスト教についてきちんと勉強するいい機会だと考えました」
立教大学YMCAクラブは当時、青森・下北半島の僻地へ行って地域振興を手伝ったり、ハンセン病の療養所を訪ねて花壇やベンチを作ったりするなど、ボランティアが活動の中心であった。ホテルマンとしての勉強とは別に、肉体を使った無償の労働奉仕という経験を重ねることで、四方さんは理屈ではないホスピタリティの本質とも言うべきものを身につけていった。

理想と現実のなかで
1969(昭和44)年に大学を卒業した四方さんは、大阪でその年の秋に新しく開業する東洋ホテル(後のラマダホテル大阪)9に就職した。初めてホテルの立ち上げに参画するなかで、ゼロスタートで創り始める面白さと難しさを経験する。同ホテルで宿泊部フロント支配人等を務めた後、1984年には、やはり新たに開業する大阪全日空ホテル・シェラトン(現・ANAクラウンプラザホテル大阪)10へ転職し、宿泊部・宴会部・マーケティング部の支配人を歴任する。
こうしてホテルマンとしてのキャリアの幅を着実に広げてきた四方さんであるが、その間、常に自問自答を繰り返していたという。
「お客様に喜んでいただくために、自分がどこまでやれるのか。そうした行動がきちんとビジネス(=利益)に結びつくのか。正直に言えば、手探りの状態でやってきました。せっかく志をもってこの世界に入ったのだから、自分ができることを100%やりたいと思っていても、20、30%しかできなくて、残りは辛抱していた部分がありましたね」
「お客様を喜ばせること」と「利益」の両立という、ホスピタリティの理想をいかにすれば実現できるか──その理想と現実のあいだで、常に葛藤が存在していたのである。
だが一方で、大阪全日空ホテル・シェラトン時代、四方さんならではのホスピタリティの表現が高い評価を受けたことも決して少なくなかった。そのひとつの例が、来日する外国人タレントへの対応である。当時はバブル全盛期にあたり、外国人タレントが大挙して日本にやってきた頃だった。
「三大テノール歌手のひとりであるプラシド・ドミンゴや、トニー・ベネット、ホイットニー・ヒューストンやマドンナらが、大阪公演に来るわけです。こうした大物タレントがうちに泊まれば、ホテルの評価が高まるし、何よりも働いている仲間たちが誇りに思い喜んでくれる。話題になって業績も上がる。それならば、積極的に取りに行こうということになったのです」
四方さんが重要なパートナーと考えたのは、外国人タレントの公演を企画・運営するイベント興行会社であった。東京にある同社の事務所に足繁く通うなか、担当者のひとりであるAさんと仲良くなり、Win-Winの関係を構築していった。
「Aさんの紹介で外国人タレントが泊まった後、その都度必ず東京へ行ってAさんに、『ホテルのことなんて言っていた? 』と確認するようにしました。そうすると、『ここらへんが良かったみたいよ。みんなに話していたわ』とか『ここはちょっと駄目よ』と教えてくれる。毎回反省点や良かった点を確認し、気になることは必ず改善するようにしました。Aさんも、タレントがご機嫌になれば嬉しいし、気分を損ねれば苦労する。と言うことは、ぼくを仲間に入れておきたいわけです。だから、『四方さん、今度○○が来るけど、取る? 』と定期的に情報をくれる。そうしたキャッチボールがスムーズにできたんだと思います」
自分が頑張れば頑張るほど、みんなを幸せにできる。一方で、どこかで手を抜けば、その影響がいろいろなところに出てくる。そうした世界にあって、四方さんは組織を巻き込みながら好循環の輪を広げていった。
「ぼくがひとりでできることなんてたいしたことないんです。イベント興行会社にも最初は一人で行っていたけど、次に行く時はレストランの責任者を連れて行ったりしました。Aさんに、『彼がうちのレストランの責任者です。タレントさんがとくに食べたいものがあれば彼がやりますから、彼に言うといいですよ』と伝えると、Aさんが教えてくれる。責任者は必死になってメモをとって、大阪へ戻ると今度は調理場のスタッフへ伝えていく。そうすると、みんながプロジェクトに関われるようになる。カッコいい言葉で言えば、やりがいを感じるわけです。そういうのがうまくいってたんですよね」


“四方流”への挑戦
ホスピタリティの表現方法は人それぞれであり、むしろ一人ひとりの個性やオリジナリティを活かすべきものである、と四方さんは考える。それでは、この頃に四方さんが実践した“四方流”ホスピタリティとは、具体的にどのようなものだったのだろうか。
「例えばマドンナが泊まれば、彼女はスタミナづくりを重視するのでホテルの周辺で走りたいわけです。ところが、当時はホテルの外に出られない。そこでスタッフ用の階段をフリーにして、ポイントとなる場所だけスタッフを立たせてプロテクトすることで、自由にトレーニングできる環境を作ってあげました11。シンディ・ローパーの場合、ホテルの2階の回廊を渡る際、1階にいたマスコミ関係者に気づかれずに移動するため、彼女と肩を組んで逃げたこともありましたね。また、トニー・ベネットは、ぼくが『昔から好きだったんですよ』と伝えたうえで、『I left my heart in San Francisco~』と彼の歌を面白半分に歌ったら、『アキ、そうじゃない。ここはこう歌え』と教えてくれました。本当に友だちの関係ですよね。彼らもホテルの中でじっとしていてもつまらないじゃないですか。そんな時、わけのわからないやつが相手になってくれるので、彼らも嫌じゃなかったみたいですね(笑)」
スターの多くはわがままであり、一人ひとりに望ましいホスピタリティがある。そのなかで四方さんが印象に残っているのは、マドンナのマネージャーの振る舞いであった。
「マドンナが公演を終えてホテルの客室に戻ってくると、マネージャーが彼女を迎える。その時、『きょうのショーは最高だったよ、世界一じゃなく宇宙一だったよ!』とべた褒めなんですよ。そうすると、マドンナもやっぱり嬉しいんですね。マネージャーとしても大事なタレントを元気づけたいから、いろいろな言葉を尽くして声をかける。そうしたやり取りを間近に見て、一流の人たちはそこまでやるんだ、と実感しました。普通は『お疲れ様』とか『きょうはよかったね』ぐらいじゃないですか。そこまで徹底した姿勢を見せつけられると、何をしてあげればいいかということが分かってくる。そこまで近づかないと、ヒントは得られないと思いましたね」
初回に泊まった時、満足いくホスピタリティを受ければ、2回目に来日する際は「大阪は全日空ホテル・シェラトンにしてくれ」とリクエストするようになる。ライバルのホテル関係者がプロモーターのところへ行くと、「四方ってやつがいて、シェラトンに泊まりたいと言っているから」と告げられる。当時は同業の大学の先輩から、「四方、おまえやり過ぎじゃないか」と電話がかかってくることも少なくなかったという。


失敗を糧に
もちろん、四方さんと言えども、最初からすべてがうまくいったわけではない。
「失敗と言われて思い浮かぶのはマイケル・ジャクソンの時ですね。彼らがステージに出れば当然汗を大量にかくので、数十枚単位のバスタオルを貸して欲しいと言ってくる。その時はちょっと頑なになって、そのリクエストをお断りしたんです。そうしたら、『お金を払えばいいのか?』『そうです』という展開になって。後でマネージャーから言われましたね、『あんなことを続けるんだったら、おたくには泊まらないよ』と。翌日、言われる前に大量のバスタオルを用意したら、事なきを得ることができました。ささやかな話ですけど、そういった失敗はありました」
失敗の経験を糧にしながら、四方さんはホスピタリティのあり様について改めて学び、より深く考えるようになっていった。
「ある意味で、半分は失敗だったかもしれないです。Aさんと一緒に怒られて、『ここらへんは気をつけたほうがいいよ』とヒントをもらって次に生かす、ということの繰り返しでした。音楽のジャンルだと、オーケストラなどいろいろな人たちが付いてきますけど、それぞれに責任者がいるわけです。ですからAさんの話を聞き、それからオーケストラなりコーラスグループの責任者の話を聞く。彼らにはAさんに言いにくい不満もある。だから、ぼくが代わりに聞いておいて、次の機会に改善する。そうすると、その責任者はすごく喜んでくれるし、Aさんにも『今回はみんな満足しているよ』と伝えてくれる」
ホスピタリティはコストを伴うものと思われがちだが、「お客様のためにやって差し上げたい」という気持ちさえあれば、その表現方法は工夫次第でいくらでもある。そしてホテルマンは、いい意味でお客様の機嫌をとり、気持ち良さを提供することができれば、お客様の仕事そのものを成功に結びつけることも可能になる。いわば、ホテルマンには無限の可能性がある、と四方さんは明言する。


ザ・リッツ・カールトンへの共感
四方さんにとって、“自分の思い”とホスピタリティの表現を、完全に一致させていくうえで不可欠だったのは、やはりザ・リッツ・カールトンの存在だったという。
1990(平成2)年、大阪全日空ホテル・シェラトンを退社後、四方さんはザ・リッツ・カールトン大阪立ち上げプロジェクトに参加し、その責任者として開業準備に携わることを決断する。日本では当時、外資合弁ホテルはことごとく失敗に終わっていた。それゆえに四方さんは、オーナーとなる阪神電気鉄道(株)と、ホテル運営会社であるザ・リッツ・カールトン ホテルカンパニーとのあいだで、3年余の歳月をかけて相互訪問を定期的に繰り返し、信頼関係の構築、異文化の理解・融合に尽力した12。プロジェクトに関わるすべてのスタッフが本音レベルの議論を丁寧に重ねるなかで、四方さんはリッツ・カールトンにおいて、ホスピタリティの実践がビジネスとしての成功を見事なまでに実現させている姿に共感する。
「自分がそれまで取り組んできたことは、よくよく考えたらリッツ・カールトンの考え方と一緒なんですよ。簡単に言えば、マドンナの友だちか親戚になった気持ちで対応すればいいんです。リッツ・カールトンの根底には、人が人として、『心』を持って関わり合う方法を模索する哲学がありました。お客様とスタッフをはじめとするみんなが幸せになってこそ、成功がある。全員の幸せを追求する結果として、利益がついてくる。ホスピタリティは、すべての人々が、ともに幸せに関わり合っていくための、生き方を表すものである、というわけです」13
日本社会において、自分さえ良ければいいという感覚や、自己責任を求める風潮が強まるなか、ホスピタリティの未来には暗雲が立ち込めているようにもみえるが、四方さんの見方は違う。
「日本はそもそもホスピタリティのレベルが高いですし、近年それが落ちているとは思いません。ホスピタリティが評価され、また必要とされる社会がいままさに到来しつつありますし、インターナショナルに活躍できる環境も整ってきています。人に喜ばれることをして、『余計なことするな』と怒られることは少ない。80~90%の人は『嬉しい』と感じるものですよ」
四方さんが明るい未来を見据えているように、「誰かのためになんとかして差し上げたい」という心を持ち、それを行動として示すことで、相手にさりげなく伝える姿勢さえあれば、ホスピタリティの精神を活かせる舞台は無限に広がっているのかもしれない。