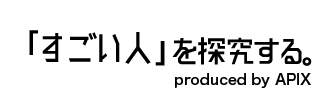「ぼくはろくでもない人間ですけど、何かあるたびに不思議な縁に守られてきました」
東京・松濤の「シェ松尾」1、神戸・北野町の「ジャンムーラン」2という日本を代表する高級フレンチレストランでソムリエ・ギャルソン、そして支配人として腕を磨き、内外のVIPをもてなしてきた前田拓己さんはこう振り返る。
その前田さんが2018(平成30)年、人生の集大成としてオープンさせたシングルオリジンコーヒー3とお酒を楽しめるカフェ&バーが、「徐庵JOAN」である。JR大阪駅から丹波路快速電車に乗って1時間強、丹波篠山の玄関にあたる篠山口駅から神姫バスに乗り換えると、商家の古民家が並ぶ宿場町の面影が色濃く残る景色が目に入る4。春日神社前というバス停で降りてすぐ、商店街から小さな路地をひとつ入った場所に、「徐庵JOAN」と書かれた小さな行灯が目に入る。
築100年以上の古民家を改装したこの店には、庭を活用したオープンテラスも含めて9卓のテーブルが並ぶ。室内とオープンテラスが一体化する春から秋にかけては、心地よい風の息づかいが心に沁みる。センスよく生けられた四季折々の花々、こだわりの音響設備から流れる厳選された音楽、客の待つテーブルで一杯ずつ丁寧に淹れられるシングルオリジンコーヒー──「徐庵JOAN」には、前田さんが求め続けてきた「心癒される空間」が見事なまでに集約されている。
至福の経験
前田さんは1958(昭和33)年、九州・福岡市で3兄妹の長男として誕生した。お父様はフィリピン生まれの日本人で、マニラで商売をしていたが、戦時中に日本の教育を受けるため福岡へ渡り、戦後は広告代理店に勤め一家を支えた。お母様はプロ並みの料理の腕をもち、前田さんが「食」の道へ進むうえで多大な影響を与えた。
「母はいつも美味しい料理やお菓子を作ってくれましたね。とりわけ小学校4年生の時、『誕生日に何を食べたい? 』と訊かれたので、『シュークリームを死ぬほど食べたい』と答えたら、たくさん焼いてくれたのは忘れられません。オーブンを開けた時の匂いも含めて、いまでも鮮明に記憶に残っています」(前田拓己さん)
食べることが何よりも好きだった前田さんは、親戚からも「食べさせ甲斐がある子ども」として人気者で、美味しいものを食べに連れて行ってもらうことが多かった。
「リアクションがいい子どもだったんですかね。周りの大人たちから結構可愛がられた覚えがあります。美味しいものは決して忘れないものです」
前田さんの育った環境は、美しい自然に恵まれ、国内外のアートに触れる機会も多かった。お母様が有田焼で知られる佐賀県・有田町の出身だったため、学校が休みになると同地の親戚の家に遊びに行った。
「窯元をやっている親戚が多く、周りに重要無形文化財保持者(人間国宝)も珍しくありませんでした。子どもの頃から窯場や作業場で遊ぶのが日常で、絵付けなども見ていましたね。また、黒髪山県立自然公園の『竜門峡』5の神秘的な渓谷美の景色も近くにあって、石切り場6などでそうした風景をスケッチしたりしていました」
こうした環境で育った影響もあって、上の妹さんは染付、下の妹さんは陶芸の世界にそれぞれ進んでいる7。
前田さんの実家では、両親が好きなクラシック音楽がよく流れていたほか、お母様がバレエのファンで、レニングラードやボリショイのバレエ団の来日公演があると、よく一緒に行かされた。
「生のオーケストラに触れる機会も少なくありませんでした。いちばん記憶に残っているのは、九州交響楽団のコンサートで、子どもにベートーベンの第5交響曲の指揮を振らせる企画があって、なぜかぼくが抜擢されましてね。フルオーケストラを前にばーんって。あれは痺れましたし、忘れられない経験です」
幼少期から少年時代にかけて、知らず知らずのうちに気持ちが豊かになる体験を重ねてきたことが、前田さんのセンスや感性の礎となる。

充電期
前田さんが故郷の福岡を離れるのは、大学進学で東京へ行った時である。周囲から理科系に向いていると言われて、素直に理科系の大学へ入学する。
「その頃、やりたいことってなかったですね。ただ、東京へ行けば何かが待っているんじゃないかって。東京への憧れというのはありました」
ところが上京後、前田さんが大学に真面目に通ったのはわずかに過ぎず、すぐに映画館やジャズ喫茶等へ足繁く通う毎日が続くようになる。
「やりたいことを探しに来たのに、いざ理科系の大学へ入るとほとんど時間に余裕がないし、周りに面白い人間もいませんでした。ぼくはどうしようもないやつなんで、大学へはすぐに行かなくなりましたね。映画は一杯観ました。あの頃って名画座がたくさんあったじゃないですか。フィルム・ノワール8について熱く語ったりとかね。あとはジャズです。ジャズ喫茶へ行って、『スイングジャーナル』や『朝日ジャーナル』を読むのが格好良かった。大人になった気分になれました」
充電期とも言える日々を過ごした後、前田さんは大学を中退し、お父様の友人が経営していた地熱開発会社へ就職する。具体的な仕事は坑井掘削調査であった。
「八丁原地熱発電所や湯布院、宮崎県えびの市などのほか、北海道の森町濁川(にごりかわ)地区へも調査に行きましたね。地熱発電に使う深さ──浅くて1,000m、長いもので1万m以上──の調査坑の掘削を行い、地熱層からどれくらいの発電ができるかを調べる仕事でした」
リーダー格の先輩社員にも可愛がられ、充実した毎日を送っていた。仕事に対する評価も高かった。ところがある日、前田さんは自分の置かれた状況に疑問を抱く。
「居心地は良かったんですけど、結局は父の庇護のもとでいい気になっていました。それはおかしいじゃないかと思ったのです。結構いいポジションで仕事をさせてもらっていたこともあり、社長も友人の息子ということで気をつかってくれているんだな、と」
普通ならば、仕事に慣れてきて、周囲から評価されている環境を、自ら捨てることはしない。しかし前田さんは、「いまのままではいけない」とあえて現状を否定し、“ゼロ”に戻るために地熱開発会社を退社する。

「食」の世界へ
大学入学後、成り行きまかせとも言える人生を歩んできた前田さんは、このタイミングで強い覚悟のもとに決断を下す。大好きな「食」の世界で生きることである。そして、大阪あべの辻調理師専門学校9へ入学する。22歳の時だった。
前田さんの生活にはいつも美味しいものが近くにあり、それが幸せの源でもあった。その気持ちを、今度は多くの人たちに自分が与えることはできないか、という思いがあった。調理の勉強に真摯に取り組んだ前田さんは、卒業後の就職先を選ぶ際、迷わずシェ松尾に決める。当時のシェ松尾は、フランスの三ツ星レストランで料理人として活躍したオーナーシェフの松尾幸造氏が1980(昭和55)年、閑静な高級住宅街・渋谷区松濤にオープンして間もない知る人ぞ知る存在であった。
「担任からいろいろな資料を見せてもらって、ここがいいな、と直感的に思いました」
辻調理師専門学校の主任教授が松尾オーナーとフランスの三ツ星レストラン「ラセール」で同期だった縁もあり、前田さんは教授を訪ねて松尾オーナーを紹介してもらう。
「夏休みの間、アルバイトとして働かせてください。それも就職試験の一環として、使えるか使えないかをみてください」とオーナーに直訴し、許可される。試用期間において、前田さんは掃除から皿洗い、グラス磨きなど、率先して何にでも取り組んだ。その姿をみた松尾オーナーは、「学校をやめてすぐに来い」と言ってくれたが、「それでは先生方に対して筋が通らないから、卒業したらお世話になります」と告げて学校に戻り、卒業後にシェ松尾へ就職した。
自然体のまま目の前の環境に飛び込み、誠心誠意を尽くす。前田さんの裏表のない真っ直ぐな姿勢は、周りの人たちを惹きつける。シェ松尾において、前田さんの「食」の世界での挑戦が本格的に幕を開けた。


ソムリエとして
シェ松尾へ入店後、前田さんは目の前の課題を一つひとつクリアしていった。
「入店したばかりの当初は何も知らないじゃないですか。だから、よく馬鹿にされましたよ。それが悔しくてね。絶対にできるようになってやる、と思いました」
入店して間もなく、常連客の一人である作曲家の都倉俊一さんから、「こんなワインリストじゃ笑われるよ、世界に。きみがちゃんと勉強しなさい」と苦言を呈される。このことをきっかけに、ワインに対する尋常でない研究が始まる。前田さんはもともとワインに関して少なからぬ知識があり、辻調理師専門学校時代にも良き先輩に恵まれ、スーパープレミアムワインの美味しさを体感していた10。そうした経験を土台としつつ、タイトルに「ワイン」と付いた書籍を片っ端から買って読破していくと同時に、ワインの試飲会にも可能な限り通った。
一方で前田さんは、仕事で遅くなると「タクシー代がないから、いいですか?」と松尾オーナーに許可を求めたうえで、店でよく寝泊まりした。その理由は明快だった。店内にあるバーでいろいろなボトルを味見しては朝まで“勉強”するためである11。
こうした努力もあって、前田さんはソムリエの資格試験に合格し、その独自の目利きでシェ松尾のワインセラーを充実させていった。
「シェ松尾はもともとポテンシャルの高いワインの品揃えが貧相だったので、お客様のニーズに合わせたワインをきちんと揃えればそれだけで売れました。売上げがどんどん伸びて、すごい年には前年比1,000%増を達成した時もありましたからね。バブルの頃って、60席くらいのお店でも、ワインだけで1カ月数千万円を売り上げたりしたんです」

お客様の啓示
この頃から現在に至るまで、前田さんの接客姿勢はいつでもお客様本位で徹底しており、決してブレることはない。松尾オーナーの著書に、その頑固な性格を伝えるエピソードが記されている。
ある日、調理のための食材が揃わず急遽買いに行かねばならなくなり、お客様の料理を通常以上に待たせることになった。ギャルソンを務める前田は、「お客さんが待っているんだから、早く出してくれ」と厨房に催促する。私が「そんなに待っていないはずだ」と応えると、「テーブルで料理を待っているお客さんの時間と、料理場で作っているシェフの時間の感じ方は違うんだ!」と切り返す。思わず「生意気なことを言うな。謝れ!」と声を張り上げると、前田は「あなたが悪い。あっちに座って実際に待ってみろ!」と客席を指さして反論する。カーっとなった私は、「ここは俺の店だ!」と怒鳴る。前田も「違う、みんなの店だ!」と怒鳴り返す。後に前田は、「シェフ、(あの時は)申し訳ありません。若気の至りでした」と謝ってきた。(『シェ松尾物語』12より要約)
こうした忖度なしの筋の通った姿勢が評価されて、前田さんは1985(昭和60)年、シェ松尾の第3代支配人に就任する。そして、多くのVIPへの接客担当を任される。
「シェ松尾は当時、勢いがいちばんあったレストランのひとつですから、いいお客様がたくさんいらっしゃいました。お客様に育てていただいたというところが大きいですね」
皇族や政財界人をはじめ、文化人や芸能人・スポーツ界で活躍する人々など多彩な面々がシェ松尾に足を運んだ。
「シェ松尾時代に学ばせていただいたお客様はいっぱいいらっしゃる。白洲次郎・正子ご夫妻は、会話もとても面白く、本当に勉強になりましたね。去年亡くなられた樹木希林さんも、ご自宅もNHKからも近いということもあって、贔屓にしていただきました。ほかの芸能人とは違い自然体を貫かれた方なので、接客していて本当に気持ちよく、またいろいろと教えてもくださった。松尾オーナーがお茶の心得があるため、その方面のお客様もいらっしゃった」
新天皇も皇太子時代に何度か来店されたほか、外務省の小和田恆(事務次官時代)氏もシェ松尾を贔屓としており、後の皇后陛下(雅子様)らご家族とのお食事でも、前田さんが接客を担当した。
どんな相手であろうとも、一切媚びることなく自然体で接する姿勢を貫く前田さんは、お客様から絶大な信頼を得ると同時によく可愛がられた。そして、個性豊かなお客様と接するなかで、料理・ワイン・会話についてのみならず、生き方そのものを学ぶことも多かった。それは、前田さんにとってかけがえのない財産となっていった。


神戸での18年
シェ松尾で刺激的かつ充実した毎日を過ごしていた前田さんに、大きな転機が訪れる。1995(平成7)年1月17日、阪神・淡路大震災が関西地方を襲い、神戸出身で一人娘だった奥様の実家が被災したのである。
「大震災の時は東京にいましたが、家内の実家が潰れて両親も身体の具合が悪くなったんです。このまま放っておいたら後で後悔すると思ったので、すぐに神戸へ移ることを考えました」
前田さんの生き方を象徴する決断と言える。その時々に何を最優先すべきかを瞬時に判断し、あれこれと迷うことなく本能的に行動する。そこには、前田さんの人生哲学を感じずにはいられない。
こうした真っ直ぐな生き方は、ここでも不思議な縁を呼び寄せた。神戸の名門フランス料理店ジャンムーランのオーナーシェフ・美木剛さんから、「一緒に働かないか」と声をかけられたのである。美木シェフは、神戸のフレンチ界を長年にわたって牽引した料理人で、ジャンムーランは多くの有名シェフを輩出しており、関西のフレンチレストランを語る上で欠かせない名店であった。また、仕事と遊びに100%心血を注ぐその姿は、多くの料理人たちの憧れの的と言えた。
シェ松尾とはまた異なる魅力と刺激に満ちた環境のなかで、前田さんは誠心誠意、仕事と向き合った。ところが、ジャンムーランに勤め始めてから5年目の2000年末、美木シェフが突然「店を閉める」と宣言する。理由は、シェフ自身の夢を叶えるためだった(*13)。
「閉店(2001年2月末)までの最後の数週間は早朝に店に入って深夜まで、座る暇もないほど忙しく、スタッフがばたばた倒れて大変でした。ありがたいことに、その頃一緒にやっていた仲間とはいまでも付き合いがありますね」
ジャンムーランが閉店した時、前田さんは42歳だった。松尾オーナーから復帰の誘いもあったが、奥様の両親のこともあって見送った。そして、これまでの経験を活かして、前田さん自身がオーナーとなるBAR「端くれ醍醐」を神戸・三ノ宮でオープンさせる。
シェ松尾で身につけた食の“醍醐味の端くれ”を、少しでもお客様に楽しんでいただきたい──そうした思いから命名されたこの店では、作り手の情熱が感じられるワインを中心とした選りすぐりの酒が多種多彩に揃い、肴は極上のチーズやオリーブの実などのほか、小羊の内臓を使った珍しい料理も味わえた。一席ごとにランチョンマットが敷かれ、しゃれた陶器に小さな花が生けられており、和のセンスがそこはかとなく感じられるしつらいとした。さらに、オーディオルームと間違えるかのような音響設備が整い、センスの良いジャズやクラシックの名曲が客の心を癒した。
「お客様に豊かな気持ちになっていただける空間づくりにとことんこだわりましたね。とくに、ある程度の音域と奥行き感のある音は絶対に再現したいと思いました」
いまでも“伝説のBAR”と呼ばれる「端くれ醍醐」は、開店から12年後、惜しまれながら幕を閉じる。前田さんはその後、神戸の地を離れて再びシェ松尾、さらに有馬温泉 御所坊を経て、還暦を機に新たなスタートを切ることになる。

篠山との縁
「アートの魅力を採り入れつつ、心が癒される時間を、コーヒー1杯で過ごしていただけるような空間を創りたい」
このコンセプトのもと、前田さんは人生の集大成としての店づくりに着手する。自らが生まれ育った福岡を拠点とし、2018(平成30)年春から具体的な準備を始めた。
「もともとは妹たちが福岡県小郡市にアトリエを構えていたので、そこで3人で一緒に店をやろうよと話し合っていました。ところが、下の妹が大きな個展を控えており、アトリエでぼくが店の準備のためにうろちょろしていたら、制作活動に集中したいからしばらく動くのはやめてほしい、と言われましてね。それで海外も含めていろいろな土地を巡る旅に出たんです」
そうしたなか、さらなる縁が前田さんの計画を変えることになる。全国で古民家再生の活動に取り組んでいる一般社団法人ノオト(note)の金野幸雄理事長14に声をかけられ、丹波篠山の古民家などを見せてもらうことになる。
「実はジャンムーラン時代の仲間が、集落丸山というここから5㎞くらい山へ入ったところで、古民家を改装してフレンチレストランを10年くらい前に開いていました。そのご縁でちょこちょこは来ていたんです。その集落丸山がノオトの原点だったんです」
紹介された物件でピンとくるものはなかなか見つからなかったが、いまの「徐庵JOAN」となる建物と出会った瞬間、前田さんは「ここだ!」と確信したという。
「まさに一目ぼれでしたね。この空間がすごく気にいったのと、篠山の原風景はやっぱりいいですよ。花を摘んできて生けるとか、理屈じゃあないんです。気持ちが豊かになるというか、穏やかになりますね。築100年以上に及ぶ木造の建物が、世界的なプロダクトデザイナーの喜多俊之先生の篠山ギャラリーKITA’S15と中庭づたいにつながっているのもよかったです。喜多先生とお話したら盛り上がって、誘われるままここへ来ちゃいましたね」


自然体の魅力を最大に
「徐庵JOAN」は2018(平成30)年11月8日、丹波篠山の地でオープンする。店名には、「このへんでおもむろに徐々にやって行こう」という前田さんの思いが込められた16。
新しい店で前田さんが目指したのは、お客様が心を癒していただける空間づくりの集大成である。そして、メインで提供する飲み物は、これまでの経験が生きるワインではなく、シングルオリジンコーヒーとした。
「ワインには本当に素晴らしい世界があるし、ものすごく魅力あふれるものです。ただ、驚くほど高価になり、いいものはとても手が届かない17。人間のいやらしい部分とも付き合わないといけない。普通じゃないよねって思ってしまう。それに比べれば、コーヒーはいくら高くても知れている。その1杯で、少しだけでも豊かな気持ちになっていただきたい、と思ったわけです」
前田さんは、コーヒー好きの両親の影響もあって、子どもの頃からコーヒーに憧れを抱いていた18。コーヒーを飲むことを許された中学生になると、サイフォンを自分用に購入し、毎日淹れて楽しんでいたと言う。それだけに、上京後も老舗喫茶店を何軒も渡り歩き、“本物”を体験してきた。
「吉祥寺の『もか』19や銀座の『カフェ・ド・ランブル』の影響は大きかったですね。『カフェ・ド・ランブル』のオールドビーンズ(生豆のまま冷暗所で10年以上寝かせた豆)などは、海外には絶対にありません。また、東京・南千住の「カフェ・バッハ」の店主・田口護さん20は、1968年の開業当時からコーヒー豆の生産国を回り、生産者たちと向き合いながら品質向上に努めてきました」
シングルオリジンコーヒーの魅力を伝えるうえで、前田さんは日本の伝統的な喫茶文化やBAR文化を大切にしている。
「BARへ行っても、海外には日本のように丁寧に作ったカクテルをきっちり注いでくれるところってないじゃないですか。美味しさを追い求めるというよりも、雰囲気や見た目のパフォーマンスが重視されており、求められるところが違います。また、日本のコーヒーには、昔から深煎りのネルドリップといった抽出方法へのこだわりがあります。日本独自に育まれてきた“丁寧に、心を込めておもてなしする”姿勢は大切にしたいですね。日本で失われつつあるこの一番大切なことを、『徐庵JOAN』ではしっかりと受け継いでいきたい。できる限りですけどね」
都会の喧騒とは無縁な独特の雰囲気があり、四季折々の自然やアートを感じられる。こだわり抜いた音響設備が奏でる音楽、そして人が人としてコミュニケーションできる優しさに溢れる──こうした居心地の良い空間にあって、身の丈に合った精一杯のおもてなしをする。それこそが、ソムリエ・ギャルソン、そして支配人としてさまざまな体験を積み重ねてきた前田さんが辿り着いた理想郷であった。
「何度も言うように、ぼくはろくでもないやつだけど、なぜかいろいろなものに守られてきました。転機を迎えるごとにご縁もいただいて、いまここに流れ着いた感じです。残りの人生はできればここで過ごしたいと思っているけど、さてさてどうなることやら」
最後まで自然体を崩さない姿勢は、前田さんの真骨頂と言える。