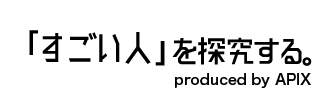三軒茶屋から下高井戸までを結ぶ東急世田谷線の上町駅の近く、世田谷通り沿いの一角に、赤い看板に白字で「手作り台湾肉包 鹿港」と書かれた店名が目に入る。小さな店内を覗くと、幾重にも重ねられた大きな蒸篭から白い湯気が立ち上り、肉まんづくりに打ち込むスタッフたちの姿が見える。朝9時の開店前からお客様の行列ができる、知る人ぞ知る肉まんの名店である。
2003(平成15)年11月にこの「鹿港(Lu-gang=ルーガン)」を開店させた小林貞郎さんは、台湾でも有数の歴史を誇る老舗「阿振肉包 振味珍」の肉まんに惚れ込み、唯一修業を許された経験を持つ。門外不出と言われた秘伝の製法をもとに、時間と労力を決して惜しまず、徹底した手作りにこだわり続けることで完成させるその逸品は、「獨有之味(オンリーワンの味)」と呼ばれるように、「鹿港」でしか味わえない唯一無二の味となっている。
偶然の出会い
小林さんは1970(昭和45)年、世田谷で開業医を営む家に生まれる。男だけの3人兄弟の末っ子として、何不自由なく育てられる。幼少期から少年期こそ病弱な体質で学校を休むことも少なくなかったが、小学校4年生になって兄たちが所属した地元サッカーチームに入ると一変する。すぐに頭角を現すとともに心身ともに鍛えられ、以来高校を卒業するまで皆勤を続けたという。
「サッカーを始めてから、実は自分にも体力があったんだと気づきました。身体は小さかったけど、根性と体力だけは誰にも負けたくなかった。ディフェンダーだったサッカーでは、ボールが急所に当たっても泣きながらボールを追いかけたりもした。どんなことがあっても諦めない粘り強さは、後々生きているのかもしれませんね」(小林貞郎さん)
大学で外国語(英語)を学んだ小林さんは、兄2人が医療の道を歩むなか、以前から決めていた日本語教師という職業を選ぶ。医師ではなかった理由は、自分なりにやりたい仕事をぶれずにやり通すことが、父・義郎さんの望むことだと思ったからであった。
「父は口数が多いほうではなく、背中でものを語るタイプでした。子どもの頃から父の姿を見てきて思ったことは、決してぶれない信念の持ち主であること。自由に好きなことをやりなさい、というように、何の干渉も受けませんでした」
1993(平成5)年の春、大学時代の同級生の紹介により、台湾の台南市1にあるYMCA 2で日本語教師を2年間務めることになる。この学校の日本語クラスは、10代の若者もいれば50、60代という中高年の生徒も少なくなかった。そのなかで小林さんは、生徒1人ひとりに対して、可能な限り親身になって日本語、その背景にある日本文化について指導する毎日を過ごす。それはやりがいのある充実した日々であった。
2年間にわたる教師生活も後半を迎えたある休日、50歳前後の女性生徒3から「美味しい肉まん屋さんがあるから行こうよ」と声をかけられる。話を聞くと、学校のある台南市から車で2時間半以上かかる彰化県の鹿港4という場所に店はあった。
「休みの日で疲れがたまっていたから、肉まんのためにわざわざそんな遠くへ行くのが嫌で一度は断った。それでも誘ってくるので渋々ながらも、彼女が運転する車に約3時間揺られて鹿港へ向かいました」
この偶然がなければ、小林さんが「振味珍」の肉まんと出会うことはなかった。同店は、もともと台湾菓子で知られる8代続く老舗だったが、日本海軍総司令官の料理長を務め、日本の和菓子店で修業したこともある先代社長の鄭振山さんが独自の技術で考案した肉包(=肉まん)が大ヒットして、肉まん専門店として台湾で知らない人がいない有名店になっていた5。
「一口食べてみたところ、びっくりするほど美味しかった。日本で食べたことのあるコンビニの肉まんとは全く異次元の食べ物でしたね。もちもちっとした食感の皮、食べた瞬間に溢れ出る肉汁のジューシーさは初めての体験と言えました。ただその時は、とても感動したものの、日本でも中華街へ行けば食べることができるものと思っていました」
小林さんはこの時、後に肉まんを作る仕事に自分が就くとは夢想だにしなかった、と振り返る。

揺るがぬ決意
台湾から帰国後、小林さんは横浜YMCAで日本語教師の仕事を2年間続けた。しかし、当時は非常勤講師の職にしか就けず、季節ごとの休みのたびにアルバイトをしなければ生計が立たなかった。
「大学時代からいまの家内と付き合っていたこともあり、いつまでもこの生活を続けるのは難しかった。自分のやりたいことだけを考えて、家族を窮地に立たせることがあってはならない。教師の仕事は定年退職後にもう一度挑戦すればいい、と決断しました」
小林さんはその後、2度にわたり地ビール6関係の仕事に転職する。最初は地ビールの作り方を教える機械メーカーのスタッフとして、次は日本酒の蔵元で地ビールを作る職人としての道を歩んだ。
「地ビールの仕事は給料が安かった。当時は日本酒が冬の時代にあって、ぼくらが一生懸命地ビールで頑張っても、待遇はなかなか改善されない。家内もぼくが生き生きしていないことに勘付いているようだったので、何とかしなければいけないと思っていました」
一方で小林さんは、「振味珍」の肉まんを思い出しては、横浜の中華街へ行ったり、有名店から取り寄せたりして試してみた。しかし、いくら探してみても、あの肉まんに敵う本物の味と巡り合うことはなかった。
「振味珍」の肉まんを自分で再現することはできないか──。地ビールの仕事で悩む日々にあって、新たな思いが浮かび始めていた。
そうしたなか、奥さんのご両親から誘われて、小林さん夫妻は神戸の南京中華街へ行く機会に恵まれる。ある店の前に肉まんを買い求めて長い行列ができている光景に直面し、小林さんもさっそく並んで食べてみた。その瞬間、がつんとくる衝撃が頭に走ったという。
「1個400円と高価だったにもかかわらず、冷凍の肉まんを蒸しているだけのようにみえました。これはちょっとおかしいぞ!! と強烈に思ったんです。やっぱりちゃんとした手作りの美味しい肉まんを食べてほしい。これは自分がやるしかない──その決心は自分でも驚くほど強いものでした7」
人の記憶というのは面白いものである。その瞬間、瞬間は「点」に過ぎなかったものが、ある時突然、「線」となり「面」となってつながっていく。小林さんのぶれない人生に向けた挑戦は、すべてここからスタートする。

“四度目”の正直
南京中華街からの帰り道、小林さんは自分の気持ちを奥さんに打ち明けた。だが、いきなり“肉まん屋”と言われても、イメージできるはずもなかった。
「最初は『えーっ、何言ってるのよ』という感じでしたね。そうであれば、つべこべ説明しても仕方ないから、台湾へ行って『振味珍』の肉まんを味わってもらおうと思った」
すぐに有給休暇を1日取って、土日を絡めて本家の肉まんを食べに行く。奥さんは、初めて口にすると同時に「めちゃくちゃ美味しい!! これなら頑張ってやってみようよ」と、小林さんの背中を押してくれた。
地ビールの仕事を継続しながら、小林さんは3回、「振味珍」を訪ね、修業のお願いをするものの、そのたびに断られる。
「そりゃそうですよね。門外不出と言われ、支店等も一切持たない。ご子息でさえもいまの店を継ぐ以外、店を持つことが許されなかったですからね。そこへ外国人である私が突然訪ねて、修業させてくださいと言っても、許してくれるわけがないと思いますよ」
奥さんと一緒にお願いした1回目は、親日家ということもあってお客さんのような扱いで店内に通され、肉まんを勧められたうえ丁重に断られたという。次に有給休暇が取れた半年後、2回目のお願いに行くも、先代社長の奥様(以下、大女将)から、「あなたが来ることによって、私の息子(=現社長)の負担になる。私たちはいまのままで十分やっているから」と断られた。そして3回目は、兄と台湾にいる兄の友人(台湾人)と3人で訪ねた。小林さんがお願いしたうえに、「こいつは本当にやりたいと思っているんです」と2人からの後押しもあったが、三度断られる。
普通であれば、3度挑んで断られ続ければ心が折れる。ところが、小林さんは決して諦めなかった。
「4回目、もう一度家内と一緒にお願いに行きました。2人で頭を下げてお願いしたけど、答えは変わらなかった。ただその時は、いままでと違って、『また明日来なさい』と大女将から言われました」
そこで小林さん夫妻は近くのホテルに泊まり、翌朝再訪する。すると、店には初めて先代社長がいらした。先代社長はかなりの高齢のうえ、パーキンソン病を患い身体が不自由だった。最後通達を受けるものと小林さんが覚悟していると、思いがけない言葉をかけられる。
「あなたのような日本人がこのタイミングでいらしたということは、日本で私が受けた恩を返しなさい、という天の啓示なんだろう」8
“阿振肉包”の生みの親によるこの鶴の一声で、状況は一変する。大女将も、先代社長がそう言うのならば修業に来なさい、と言ってくれる。2001年3月のことだった。
4度目の修業依頼から日本へ戻った小林さんは、地ビールの仕事に区切りをつけた2001年8月、肉まん職人に向けた修業をスタートさせる。



修業時代
台湾での修業は、日本の徒弟制度とは異なり、丁稚奉公のようなことは一切なかった。毎朝6時半に店へ行って、10人ほどいる若いスタッフと一緒にひたすら皮を包む。17時半に仕事が終わり、疲れ果てて帰って寝る、という毎日の繰り返しだったという。
「現地のスタッフと同じ作業をしながら、見て真似て、わからないことがあれば聞いて確認しながら覚えていった。いまのようにクーラーの利いた快適な環境とはほど遠く、当初は夏だったこともあって死ぬかと思うほど暑いところでやっていました」
もちろん、技術の修得に魔法はなく、数をこなしながら身体で覚えていくしかなかった。基本的には皮を包む練習をひたすら繰り返す日々が続いた。途中の休憩はわずか15分しかなく、その間に昼食も済まさねばならなかった。
「身体は本当にきつかったですね。スタッフはみんな20歳前後で、兵役9に行く前の連中でした。そのなかでぼくだけが30歳を過ぎていた。でも、途中で逃げ出せばすべてが終わる。大女将に、ちょっとでも疲れた表情を見せれば、『帰りなさい』と言われるんじゃないかと。きついことをなんとか隠しながらやっていました」
小林さんにとって大女将は、特別の存在であった。仕事に対して厳しい反面、一生懸命に取り組む者には優しく、その姿勢は決してぶれることがなかった。小林さんにとって父と同様、大女将の目にはすべてがお見通しのように思えた10。
修業期間はとくに決まっていたわけではなく、「自分で納得できたら独立しなさい」と言われていた。ただ、当時は観光ビザ11だったため、1回のビザ発行で1カ月しか台湾滞在を許されなかった。このため、1カ月滞在しては日本に戻り、数カ月後に再訪するかたちを取らざるを得なかった。
「修業で台湾へ行ったのは全部で6回かな。帰国するごとに、自分なりに聞きたいことや確認したいこと、できないことなどをまとめておき、修業再開時に解決していきました。経済面については、帰国時にアルバイトをやったものの、基本的には家内が働いたお金を使わせてもらった」
一方で小林さんは、修業に入った初日、店からすべてのレシピを教えてもらえた。ただ、そのレシピには特別な材料は一切書かれていなかったという。豚腿肉、小麦粉、台湾油ネギ12、砂糖など、家庭でも普通に揃えられるものばかりだった。ただし、作り方は特別であった。まず肉まんの皮づくりが尋常ではなかった。
「種明かししてもかまわないから話しますが、讃岐うどんと同じですね。とにかく何回も何回も生地を延ばすんです。使う水もかなり少ない。それで生地をこねると、固いため徐々に指の爪が変形してきちゃう。他店では餅のように柔らかい生地を使っているけど、この店では相当の力を入れないと包めないほど生地はしっかりとしていました」
讃岐うどんを足の裏で踏んで腰をつくるのと同じことを、手で時間をかけてやるため、想像以上にきつい肉体労働となる。とにかく手間と労力を惜しみなくかけて手作りを徹底していた。また、膨らし粉や重曹、ベーキングパウダーは一切使っておらず、発酵はイースト菌に任せる。すべてが大量生産には不向きな製法であった13。
こうした“究極の肉まん”づくりは、小林さんにとってかけがえのない本物の凄さを教えてくれた。それは単なる技術やノウハウではなく、一切の妥協を許さない信念の証とも言えた。そして、その極意を会得した小林さんは、2年弱にわたる修業に区切りをつけて台湾を後にする。


苦難の連続
日本における出店準備は、苦難の連続であった。理想とする出店場所は、商店街ではなく比較的大きな通り沿いであることと、馴染みのある土地という2つだった。後者は、知らない土地で失敗すれば場所のせいにしてしまうためである。
この2つの条件を胸に不動産探しが始まるが、想像以上に厳しい現実に直面する。
「連日のように不動産店を訪ね歩いても、肉まん屋を開くことがわかると、紹介さえしてもらえませんでした。当時は不動産もまだ売り手市場で、まったく相手にされない日が続いた。自分の努力ではどうにもできず、さすがに泣きたくなりましたね」
半年近く月日が経ったある日、現在の物件を紹介してくれた不動産店と出会う。
「そこの社長さんがぼくの夢を理解してくれたからこそ、いまがあります。もともと飲食店はNGと貼り紙がしてあったけれど、どうしてもやりたいとお願いすると、オーナーを説得してくれて借りることができました」
小林さんの願いどおり、子どもの頃から馴染みのある世田谷通り沿いであった。
「たまたまですが、祖父のお墓が松陰神社14にありました。世田谷通りを喜多見から三軒茶屋まで何回歩いて往復したことか。祖父が呼び寄せてくれたのかもしれません」
一方で、肝心要の肉まんづくりにおいても難題が待ち受ける。まず皮の再現である。
「台湾では『中力粉』15と言われる小麦粉を使っていたので、日本でも同じような粉を使ったけれど、どうしてもあのもちもち感のある皮を作ることができない。いろいろな小麦粉をブレンドしてみても、正解には辿りつけませんでした」
最終的には台湾で使っていた粉を取り寄せて、大手製粉会社の営業スタッフに相談したところ、技術センターで分析した結果をもとに、パン用と麺用という2種類の小麦粉をブレンドすることを薦められた。パン用の小麦粉だけだと膨らみすぎてしまうが、麺用の小麦粉を適量混ぜることでそれを抑えて、もっちり感を醸し出すことができた。
もう一つの難題は、美味しい肉汁の再現であった。ジューシーな肉汁は、新鮮な豚肉を生のまま包んで蒸すことによって生まれる16。「振味珍」と同様、上質の豚腿肉を使って餡を作ってみるが、どうしても肉汁が濁って同じようにはいかない。
透明でジューシーな美味しい肉汁──これを実現するまでに、半年近くにわたり試行錯誤が続けられる。そして、知り合いの紹介で豚肉直販店に相談した結果、「価格は高くなるけど、上質の豚バラ肉を使ったらどうか」とアドバイスを受け、ようやく解決できた。
「いろいろな方々が協力してくれたお陰で、なんとか『振味珍』の肉まんを細部に至るまで完全に再現することができました。皆さん、肉まん屋という物珍しさもあって興味を持ってくれたんだと思いますが、本当に助かりました」

嬉しい悲鳴
2003(平成15)年11月、手作り台湾肉包「鹿港」は、いくつもの苦難を乗り越えて念願のオープンを果たす。お客様から受け入れてもらえるだろうか、という小林さんの不安をよそに、予想をはるかに超えるお客様が開店初日から駆け付けた。
「店はめちゃくちゃに賑わいました。スタート時は、ぼくと家内とパート・アルバイトの4人しかおらず、どんなに頑張っても1日に作れる肉まんの数は500、600個17。それも、夜中の2時半から家内と店に来て作り出して、パート・アルバイトに7時頃から来てもらってやっとです。夜8時には翌日の仕込みが始まる。とにかく無我夢中の毎日だった。子どもたちの面倒はすべて祖父母に任せっきりでした」
連日、お客様は店前に行列を作って並んでいる。その賑わいが世田谷通りを走る路線バスから見えたため、格好の宣伝となって人気に拍車をかける効果がもたらされた。
天手古舞の状況は1年弱続いた。その間、友だちや知り合いが土日だけ手伝ってくれたりして乗り切った。開店1年後、男性スタッフがもう一人いないと限界になったため、スタッフを少しずつ増やしていった。
「この時期を耐えられたからこそ、いまがあると思います。家内はとても根性があったし、パワフルだったので救われました。ぼくがぐったりしている状態でも、家内が『さあ、やろうよっ!』と引っ張ってくれましたからね」
開店当初のメニューは、肉まん、あんまん、まん頭の3種類だった。修業時代の「振味珍」にはあんまんはなかった18が、「年寄りの男はあんまんが好きなんだよ。絶対にやったほうがいい」(不動産店社長)というアドバイスを受けて、小林さんが1週間で考案したオリジナルである。
「ラードを練りこんだしつこい餡は好きじゃなかったから、さっぱりとしていてさらっとした優しい餡がいいと思って作りました」
鹿港にはその後、カレー肉まん、辛口肉まん、黒糖まんのほか、豆乳と冬瓜茶がメニューに加わっている。ただ、小林さんは、基本となる肉まんをベースにした商品や、台湾の伝統文化を伝えるものしか店に置く気はないと言う。
「カレー肉まんは、スタッフから出たアイデアをもとに商品化したものです。本格的なカレールウを使えば違和感があるけど、あくまでも肉まんをベースにしてあればいいなと。スムージーやマンゴー、タピオカといった流行りものはうちの店には合わないし、やるつもりは全くないですね。そこはある意味で時代に逆行してもいいと思っています」


信念の人生
「鹿港」はその後順調に知名度を高めており、著名人が「差し入れ」等に大量購入するなど、根強いファンが増え続けている。そこまでの評価が確立されているのであれば、店を拡大したり、支店を出したりするのが普通のビジネス感覚だと思われる。ところが小林さんは、かたくななまでにそれを否定する。
「本家である『振味珍』が一切支店を出していないのは、自分(=社長)が責任を持って作らないと味が落ちるためです。ぼくもいまとなればとてもよく理解できます。いかにして味を落とさず、常に同じレベルを維持できるか。いまでさえ気候条件の変化もあって、満足のいく味を保つことは難しいですからね。それなのに、もう1店舗増やして、自分と同じ理解力や覚悟、信念を持って取り組める人がいるかと言えば、それはなかなか難しいでしょう」
自分の信念を貫き通す小林さんの姿勢は、父から受けた影響によるところも大きい。当初は「肉まん屋なんてとんでもない」と笑っていた父も、「鹿港」を出店させてからは認めてくれて、「美味しい」と言って食べてくれているという。
「最近、身体の具合を悪くしたこともあって父と接する機会が増えるなか、ぼくにも同じ血が流れているんだな、と改めて実感するようになってきました。ぼく自身のすべてのベースにあるのが、『父を納得させるにはどうすればいいか』という問いでした。だから、父に何を聞かれても、答えられるだけの準備をしてきた。自分の芯には常に父の存在があったんですね」
小林さんはさらに、こうもつけ加える。
「あれだけ修業を断り続けていたのに、最終的には受け入れてくれて親身になって接してくれた人たちに対して、いい加減なことはできない。彼らの顔に泥を塗ることだけは絶対にやってはいけない19。それこそ父じゃないけれど、一本筋の通った信念があれば、決して難しいことではない。自分の磁石にくっつかないものは、はじけばいいだけの話です。そこだけは絶対に妥協したくない」
阿振肉包の生みの親である「振味珍」の先代社長の“信念”が現社長、さらに小林さんへと受け継がれた。次に小林さんの“信念”をしっかりと受け継ぐ人が現れた時、「鹿港」の肉まんも“伝統の味”へとさらに進化していくことになるだろう。