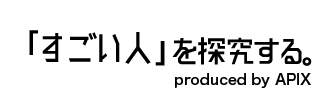絵本・児童書の専門店「青猫書房」の店主・岩瀬惠子さんが店に立つのはほぼ週末が中心である。平日は、長年勤めてきた土地家屋調査士事務所で仕事をしているからである。
「年齢的にもダブルワークはきつくなってきたんだけれど。これからの抱負? 何とか生き延びていくこと。夢がなくて申し訳ないけれど、それがいちばんの望み」
長年の出版不況とネット書店の伸長で、街の書店が次々と姿を消していく中、岩瀬さんは両親の土地にあえて同店を立ちあげ、守ってきた。立地からすれば、マンションもしくは事務所・店舗として貸してしまったほうが経済的によほど安心できたというが、やりたいこと、やらねばならないことを実現する「場」を守るため、岩瀬さんは二足の草鞋を履き続ける。
生まれ育った赤羽の地で
2014(平成26)年12月に開店した青猫書房は、JR赤羽駅から徒歩10分ほど、LaLaガーデン(赤羽スズラン通り商店街)から道2つほど入った住宅エリアとの境にある。都内でも珍しい木造4階建てビルの1階で、このビルは岩瀬さんが、ご両親の所有している土地を活かして建てたものである。庶民的な店が立ち並ぶ赤羽ならではの商店街と、外装は白、内装は木の温かみを基調に設計されたこの瀟洒なビルにはかなりの落差があるが、そのたたずまいは、岩瀬さんが「青猫書房」を開いた際の想いの一端をかたちにしたものだった。
相続対策でマンション経営がもちあがっていた時期に、岩瀬さんは自分が今後の人生を過ごす場を考えていた。どうせなら、1階部分に自分が自由に使えるスペースをつくれないか、そうすれば児童書・絵本の専門店を開ける――そう考えた岩瀬さんは、あちこちに相談してなんとか実現への見通しを立てた。
「こう見えても慎重派ですし(笑)、書店経営の厳しさは聞かされていたので、建設費はアパート部分(2~4階)の収入だけで返せなければ店が続けられない。なんとか大丈夫そうだ、といことで青猫書房をつくることを決めたんです」
一方、ビルの設計では、やりたいことのひとつである“地元への想い”を優先して少し無理をした。岩瀬さんは、1954(昭和29)年にこの地に生まれ、小学校・中学校も地元、高校も公立と、根っからの赤羽っ子である。
「気さくで飾らなくて、安いお店も多いし、とても住みやすい街です。ただ、あまり文化的な場所がないのがずっと残念でした1」
いくつかの建築企画案を模索するなか、木造に力を入れている内海彩という女性建築家がいるとのアドバイスを得た。調べてみると、23区で唯一、基本的には木造が許されない防火地域に、耐火性などの問題をクリアして4階建ての建物を設計した建築家だった。
不安な要素も多かったが、「おもしろそうだから」と岩瀬さんは、内外装とも基本的に内海氏に一任した。結果は、魅力的な場になったものの、予算も工事期間も予定をオーバーすることになる。
「内装では、お金が足らなくなってしまったんです。でも、内海さんが『ここまでやったら最後までやらせてほしい』と言ってくださって」
こうして1階を青猫書房、2~4階を賃貸マンションとした「Timber House(木の家)」は完成した。知人に「この人に頼む岩瀬さんがすごいんだよ」と言われた同ビルは建築雑誌に取り上げられ、青猫書房は建物・空間の有り様も含めて、文化発信の場として立ち上がった。

図書館勤務で児童書修行
「青猫書房」は、手前が店舗、奥がカフェで、書籍は壁面の書棚と木のボックスを組み合わせた3つの島に並んでいる。レジ前には岩波書店の少年文庫や「ゲド戦記」シリーズ、福音館書店の「パディントン」シリーズなどが並んでいて、総数約4,000冊、総じてオーソドックスな品揃えになっている。
岩波書店の「子どもの本」シリーズ2(1953〈昭和28〉年創刊)や福音館書店の「こどものとも」(1956年創刊)は、岩瀬さんの生まれた頃に出版が始まった歴史あるシリーズである。
「両親はとりたてて教育熱心でもなく、本に携わる仕事でもなかったので、家には明治神宮かどこかで買ってきたイザナギノミコトの絵本くらいしかなかった。私の5~6歳くらい下からは、絵本文化がぱぁっと花開いてきた時期に当たるんですが、それより前はまだ絵本に手が回らない時代だったと思います」
それでも岩瀬さんは、小学校の図書室で、岩波書店の「子どもの本」シリーズを読んでいたことを今でも覚えており、高学年になると「ドリトル先生」シリーズ3などにも親しんだ。中学から倉多百三やヘッセ、有島、太宰などへと移っていった岩瀬さんが、児童書に本格的に出会ったのは勤め先である。東京都港区の公務員となり、一般的な事務に携わったのち、図書館に配属された。この区立図書館勤務で、本に敬意と情熱をもつ人たちに接するとともに、児童書に関する基礎的かつ体系的な知識を身につけることができた。
「ちょうど図書館が力をつけてきた時期で、理想として『図書館の自由に関する宣言』(1954年発表、1979年改訂)を掲げて、住民の知る権利を社会的に保証していく“知の砦”として、自負と誇りをもっている人が大勢いたんです。今のように企業に運営委託するなんて考えられない雰囲気がありました。子どもの将来を考えて、児童図書の専門司書を育成しなければ、という動きも起こってきて、都立日比谷図書館の児童書担当の方がものすごく力を入れて、都もバックアップして何度も研修を開いていました」
こうした熱気ある動きの中で、岩瀬さんは頻繁にこれらの研修に行かせてもらった。当時の図書館には、最年少者が児童書担当という暗黙のルールがあり、反発する者もいたが、岩瀬さんにとっては幸いした。当時は知る由もなかったが、研修の講師陣は一流で、絵本・児童書にはどういったものがあり、子どもにとってどの本がなぜいいのかを、系統的にきちんと学べたからである。

読み継がれた本をバトンとして
岩瀬さんが図書館に配属された1976(昭和51)年は、クレヨンハウス4(港区北青山)の開店などで、世間的にも、優れた絵本や児童書は大人が読んでもいいもの、という認識が広まっていった時期にあたっていた。青猫書房開店の際に後押ししてくれる田中和雄さんがオーナー兼編集者である童話屋の設立も同じ年である。こうして、図書館の仕事にやりがいと楽しさを感じて打ち込める7年の時間がすぎていくが、岩瀬さんにも公務員の宿命である転属がやってくる。
「結婚して子どもがなかなかできなかったこともあって、それを機に公務員を辞めました。そうすると、次々に3人の子どもを授かり、そこからは絵本や児童書を子どもたちと楽しむ日々をしばらく送りました。実感したのは、大人が子どもに本を買って読んだり与えられたりするのは、10年もないということです。小学校3、4年になれば、もう読めと言っても読まないでしょう。冊数にしても、それほどたくさんは与えられない。そうであれば、多くの人間が選んで読み継いできたいいものを、少しでも子どもに手渡して読んでもらいたい、という想いはさらに強くなりました。子どもの本はロングセラーも多くて、長いものだと発刊から100年、そこまでいかなくても50年以上読まれてきた本がかなりあります。こういう考えには賛否あると思いますが、そうした本を共通体験としてもって大きくなってほしい」

後押ししてくれた“人”
10年ほど子育てに専念し、一段落したことを契機に、岩瀬さんは知人の誘いで、土地家屋調査士事務所で勤めを始めた。経理事務ながら、仕事の話に加われないとつまらないので測量士の資格をとったことにも、岩瀬さんらしさがうかがわれる。
仕事と家事の二足の草鞋で時間的余裕がない中でも、岩瀬さんは、児童書に関する講演会や勉強会などにはできるだけ足を運んでいた。とはいえ、子どもの本専門の書店を開業する、ということは、ほとんど考えたこともなかったという。「青猫書房」誕生への歩みは、“天の時・地の利・人の和”が揃ったことで始まった。
ご両親が老境に入って、自宅の土地活用としてマンション建設を考えたこと、が“時と地”。そして、この話が持ち上がってからしばらくして、童話屋の田中社長と話をする機会をもったのが“人”である。田中社長の名前は図書館勤務時に知っていたが、たまたま手伝っていた高校の同窓会の事務仕事を通じて先輩である事を知り、会食することができた。
「店を始めるときに、これから死ぬまでの10年か20年、最後の自分の時間は社会に還元したいと思ったんです。それもあって、田中さんに『素人には本屋なんて無理ですよね』と。できるとは思っていなかったので、真剣に聞いたわけではないんです。ですが、田中さんは『君、本当にやりたいなら応援するよ』と言ってくれました」
田中社長は博報堂出身だったこともあり、子どもの本への深い想いや文学的センスだけでなく、販売やマーケティングにも通じていたという。
「童話屋の書籍を扱ってくれる個人的な代理店を募集するとか、売る仕組みなども工夫されていた方です。こういう方だから、前向きに後押ししてくださる言葉が出てきたんだと思います」
書籍・雑誌の販売額は1996(平成8)年をピークに減少を続けており、2008年にはスマートフォンが登場して厳しさは加速していた。普通なら、もはや安易に新刊書店開業を勧められる時代ではなかったのである。それでも田中社長が岩瀬さんを後押ししたのは、相通じる想いがある5と感じてではなかったか、とも思われる。
青猫書房のレジに最も近いところには、今も「のはらうた」などの児童書シリーズや茨木のり子さんや谷川俊太郎さんの詩集など、童話屋の出版物を集めた棚がある。


「やばいぞ、この業界は」の一言に、守り最優先の店づくり
童話屋の田中社長は、言葉通りに岩瀬さんを応援してくれた。
新刊書店を開くのに許認可はないものの、取次(卸)との口座開設が高いハードルになる。新刊書は、岩波書店や福音館書店など買取制(本屋が本を買って仕入れる)をとる一部の出版社を除き、取次を通して書店に販売を委託、実際に売れた分を出版社・取次・書店で分けるという独特の流通方式をとる(だから売れなければ返品できる)。このため極言すれば、大量に仕入れた本を売り払って姿を消すという悪質行為もあり得ることから、取次との取引開始には信用が重要になる。児童書の場合、クレヨンハウスが中心となって、書店を開きたい人を保証する団体もあるが、返品しない、という条件を承諾する必要がある。本が焼けて(経年で茶色くなる)ダメになるなど、返品できないリスクは大きいため、岩瀬さんは取次からの仕入れを基本にすることにした。
田中さんは教文館6などの名門書店に相談したうえで、取次の栗田出版販売の主要取引先である南天堂書房7(文京区本駒込)の奥村弘志氏を岩瀬さんに紹介してくれた。その時、奥村氏は応援を約束しながらも、岩瀬さんに「本当にやるのか? やばいぞ、この業界は」と言ったという。出版・書店業界の厳しさは頭ではわかっていたが、重鎮の飾らない率直な一言は重みがあった。
このこともあって、岩瀬さんは、児童書店での利益がなくても生活できる仕組みづくりに、さらに念を入れた。続けなければ、“場”としての意味がない。すでに赤羽のある北区でも、店舗を賃貸しして休業(実質廃業)してしまう街の書店は多くなっていた。
まず、自身はオーナーながら、二足の草鞋を履くことにし、賃貸部分の管理人手当(掃除・庭整備等)と合わせて、生活のための最低収入を確保する。店長は定年退職して年金収入のある図書館時代の先輩に、協力してくれるよう懇願した。そして岩瀬さん、岩瀬さんの娘さんと3人で回して、人件費がほとんど発生しない布陣とした。
華やかさは店舗に任せ、あとはぎりぎりまで節約する――新刊書店業界で小規模な店を続けるために、岩瀬さんが選んだ戦い方だった。

いきなりの試練と厳しい経営
こうして2014(平成26)年12月、青猫書房は開店する。
店名は、開店前に迷い込んできて、店内装飾のきっかけとなった黒の愛猫からで、「黒猫」では宅配便のようなので、黒い馬を「蒼毛」というのに倣って「青猫書房」とした。
ところが、口座を開いた半年後に、栗田出版販売が会社更生法を申請して倒産してしまう。保証金は半分しか戻らず、本も入らず、再建のための追加出資を求められる可能性もあった。いきなりの試練だったが、幸い、扱いの多い岩波書店・福音館書店は買取制なので仕入れることができ、追加出資要請もなかったので何とか乗り切れた。
それでも経営は予想以上に厳しく、3年目までくらいはカフェスペースをイベント用に貸し出す場合の料金値上げなど、いろいろ試行錯誤を繰り返した。
「だけど、やればやるほど苦しくなりました。そこで税理士に相談して、借金さえ膨らまなければ続けていけるでしょう、という結論をもらって肩の力を抜き、細かい帳尻合わせの努力はやめました。その後は売上もお客様も少しずつだけれど増えています。まだまだ事業としてみれば、やっていられない数字ですけれども」
子どもたちを含めた“忙しさ”も、逆風になっている。
「開店前は、もっと子どもが連れ立ってくると思っていましたが、ほとんど来ません。考えてみれば、学校の課外授業や塾があるせいか、街を連れ立ってうろついている子どもがもうほとんどいないんですよね。子どもがスケジュールとか、自分への損得だけで動くようになると、本屋はつらいですね。そういう発想から一番遠い商売で、ふらっときて、ああいいなで買ってもらうところですから」


くつろげ発信もできる“場”を持てた者の使命として
青猫書房のカフェスペースも、岩瀬さんが「やりたいこと」「やらなければいけないこと」をするための大切な“場”である。購入してもらった本をゆっくりみてもらうだけではなく、月3~4回行われる絵本の読み聞かせ会をはじめ、絵本の展示会即売会などほぼ途切れなくイベントが催される。
読み聞かせ会は、子どもたちだけではなく、お母さんたちに絵本の魅力を実感してもらう場である。スタッフがページを繰り、読み上げると、乳児は手足を動かし、幼児は目の輝きや表情で興味と喜びを示す。
「絵本は読んであげるのが基本なので、お母さんだけでなく、お父さんにも積極的にやってもらいと思っています。少しずつですが、来店するお父さんも増えていますし。膝に抱っこして本を読んであげるって、子どもと接するにはいちばん敷居が低いんですよ。忙しくても20~30分はこういう時間をもってもらいたいと思います。子どもはすぐに寄ってきてくれなくなりますから」
もうひとつ、絵本専門店としては異色なのが、読み聞かせや絵本の展示会に交じって開催される、連続射殺事件で死刑となった永山則夫8氏に関するセミナーである。高度成長の末期に起こった同事件では、両親に捨てられ、長じても職を転々とせざるを得なかった過酷な半生を永山氏がつづった手記『無知の涙』がベストセラーになった。永山氏に関するセミナーは、たまたま来店したお客様が、永山氏に最後に面会し、その日記のほとんどをもっていた方だったことから始まった。
「永山さんの書いた『無知の涙』は発刊時に読んでいたので、とても驚いて。その方は個人で資料館をやっているけれど、常時開館ではないですし、貴重なものをより広く伝えなければという想いから始めました。その方が、『永山が小さかった時に、ここにあるような本を1冊でも読んでいたら違ったろうに』と言って涙ぐんだんです。それを見て、ここでやる意味があると思いました。永山さんのような子が、ここに来てくれればいちばんだけれども、心配している人がいる、いてもいい場所がある、というのを伝えるのは、こういう空間をもっている者の使命というか。東日本大震災以降、現地の写真を撮り続けている知人の写真展も毎年3月にやっています。都会じゃもう風化しているけれども、まだ終わっていないことです」
異色といえば、青猫書房には、童話屋の大人向け書籍のほか、絵本・児童書ではない棚がもうひとつある。戦争や憲法などに関連した書籍の棚である。
「時代的に、少しきゅうくつさを感じています。好きな時に好きな本を好きなように読めるのは、究極の自由のひとつです。これができなかった時代があり、そういう時代がまた来たら絶対に嫌という気持ちもある。憲法の本は、国の根幹にかかわることを言葉や字面のカッコ良さ、イメージ重視のCMなどで左右されるのは怖いことですし、きちんと学んでほしいという意味で置いています。子どもは『未来』なので、今やれることをやらないのは大人として無責任だという想いもあります」
この店には、フランスの詩人にしてレジスタンスの闘士でもあったポール・エリュアールの詩を絵本にした『自由』9も置かれている。
赤羽では数少ない「文化的な場所」=青猫書房には、センスのいい空間に、児童書の長い歴史や、本を並べ情報を発信することの大切さと自負、親から子へのバトンの受け渡しという営み、そして自由といったことへの岩瀬さんの想いが幾重にも折りたたまれている。
本という媒体、新刊書店という事業、弱き者への想い――いずれも旗色は芳しくない。そうしたなかで、読み継がれてきた児童書を、そして人への想いを、お母さん・お父さんへ、そして子どもたちへと伝えていく“場”を何とか守り続ける岩瀬さん。「後退戦こそが文明だからな」という言葉をその姿にみる。