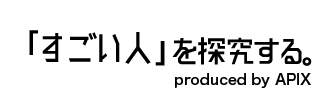埼玉県で学校図書館司書を務める木下通子さんに話を伺いに行く日の朝、新聞にある記事が掲載された。記事のタイトルは「川口祖父母強殺の元少年 『こども応援ネット』にメッセージ」。2014(平成26)年、川口市のアパートで高齢の夫婦の遺体が発見された。二人の孫にあたる17歳の少年が窃盗・強盗殺人容疑で逮捕され、有罪判決を受けた。事件後の報道によって少年の生育環境が明らかになった。義父の暴力にさらされ、母がギャンブルにつぎ込むお金のために働き、ラブホテル泊や野宿を転々としながら幼い妹の面倒を見ていた。彼は小学校5年生から逮捕時まで学校に通っていない「居所不明児」だった。事件時に祖父母宅を訪問したのも、もともとは母の指示で借金を申し入れるためだったことも分かった。少年は居所不明とされていた期間、断続的にでも学ぶ機会を求めてフリースクールに通っていた。(参考:『誰もボクを見ていない』1)
2019年現在服役中の彼は、子どもの貧困の連鎖を解消するために設置された「こども応援ネットワーク埼玉」に向けてコメントを発表した。事件後に自身に対して無条件に手を差し伸べた人々の存在に触れ、「こうして“今”はある。多くの人に出会って、多くの可能性を得た」とした。木下さんは、「人は支えられ、学ぶことで変わる」と書き、この記事をSNSにシェアした。
大人ばかりに囲まれて
木下通子さんは、1964(昭和39)年に東京都で生まれた。音楽プロデュース関連の仕事をしていたお父さんは、お母さんとともに「おしどりプロダクション」という芸能プロダクションも運営しており、詩吟の歌い手でもあった。当時は裕福で、月曜日はピアノ、火曜日は日本舞踊……という生活で、いわゆる「お嬢さん」として3歳頃まで育つ。事務所を兼ねていた自宅には音楽関係の芸能人が出入りしており、歌手の三波春夫2さんに抱っこされた幼い木下さんの写真が自宅にはあったと言う。
そうした暮らしが大きく変わったのは、幼稚園に入った頃だった。「いろんな人からいろんな話を聞くのでどれが本当かちょっと分からないんですけど」──事業が傾き、借金がかさんで両親の喧嘩が続き、お父さんが家を出た。少しあとにお母さんは駆け落ち。残された木下さんを、同居していたお祖母さんが住み込みの家政婦として働きながら育てた。そこへお母さんが「ひょっこり」帰ってきて、書店での仕事を見つけて就職する。一家は書店のあった埼玉県川口市に移転し、女3人の暮らしが始まった。木下さんが小学校1年生の時だった。
「お祖父さんやお父さんのいる暮らしの記憶がないから比べられないし、生活は楽ではなかったと思うけれど、楽しいことも多かった。女3人は気楽だったし、母はハイカラで外に出るのが好きだったから、二人で銀座や上野に行って、博物館をみてから美味しいものを食べて帰って来るようなこともありました」
仲が悪かったわけではないお母さんとの関係は、しかし今の言葉で言えば「共依存」と言えた。お母さんからの評価をいつも意識し、満たされない思いが常にあったと言う。
再婚したお父さんが住む家には、月に1度訪問していた。養育費を受け取っていることをお母さんからくりかえし言われていたため、幼い立場で気を遣っていた。お父さんも新しい奥さんも木下さんを喜んで迎え、美味しいものを食べさせてくれた。「泊まって行ったら」と言われ、断れずに夜中のトイレで泣いたこともある。
複雑な思いをいくつも抱えつつ、「ほら芸人の血が流れてるから」と本人が言うとおり、木下さんは人前で物怖じすることのない子どもでもあった。ピンキーとキラーズ3が大人気だった頃はまだ家庭が裕福で、シルクハットを買ってもらって真似をした。小学校に入ってからはキャンディーズ4やフィンガー5 5が流行り、ヒット曲を覚えては友だちと一緒に歌った。
「その頃は歌手になりたいと思っていました。その頃というか……ある程度大人になってからも。大学生の時にカラオケブームが起きて、その時にはもう司書だった(後述)けれど、私つくづく歌手に向いてたわ、なんでこんな地味な仕事してるんだろうって(笑)」

物語が授けてくれるもの
お母さんの仕事の関係もあって、木下さんのそばにはいつも本があった。海外の児童文学──とくに好きだった作家は『ふたりのロッテ』『飛ぶ教室』などのエーリッヒ・ケストナー6や『クローディアの秘密』などのカニグスバーグ7。岩波少年文庫シリーズをどんどん読み、『赤毛のアン』や『大草原の小さな家』などにも夢中になった。さまざまな物語のなかで遊び、主人公と触れ合い、主人公の身に起きたことを自分のものとして喜んだり悲しんだりして、力をもらって現実の世界に戻った。
「自分がグリーンゲイブルス8や開拓時代のアメリカ9に行ったような気になって、心がそこに飛ぶの。物語をたくさん読んだ子ども、つまり物語のなかに入り込める子どもは、主人公になれるのよね。自分の人生を、その物語の主人公の立場で見つめることができる」
その力は、恵まれない環境に置かれたり、大きな壁にぶつかったりした子どもが未来を拓くために、とても大切な力になる。木下さんは、3人のお子さんが小さい頃、読み聞かせのほかに、それぞれを主人公にした自作の物語を聞かせていた。仕事中にお子さんから「さみしい」と泣き声の電話がかかってくると、空想の小鳥や動物になって語りかけた。いつも車に置いてあるはずのお子さんのお菓子を木下さんが食べてしまって、「お母さんここに来る途中におなかをすかせた小さなウサギに会って……」と言い訳して叱られたこともあった。
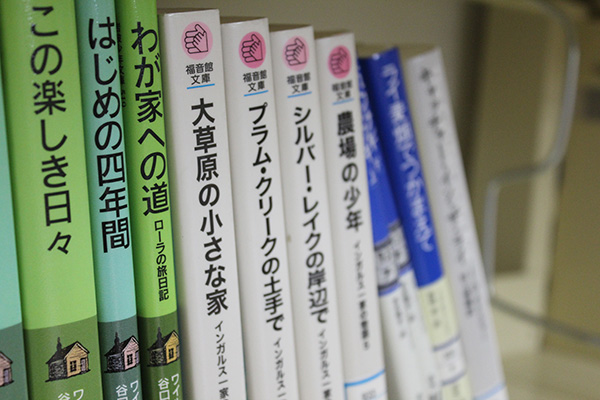
二十歳の司書
木下さんは高校に奨学金で通い、担任の先生のアドバイスで大学進学も視野に入れた。母子家庭の育ちであることを意識させられていたこともあり、知力・学力をきちんと身につけたかった。文学が身近で、安定した職業であることから、国語の先生になりたいと考えていた。しかし志望校に合格できず、東洋大学の2部(現・イブニングコース)に入学、日中は大学図書館でアルバイトすることになった。
9時から17時まで図書館で働き、18時になると講義に出席するという生活がスタートした。図書館職員の人々に「とにかく可愛がってもらった」と言うように、図書館での仕事の内容だけでなく、社会人として必要な意識やマナーなどもすべてここで学んだ。二十歳の成人式も職場で迎え、先輩たちに祝ってもらったと言う。そして大学3年生になった頃、キャンパスの近くにあった大正大学で司書資格のためのスクーリングが実施されることを知る。
図書館でアルバイトするなかで、司書の仕事への興味も高まっていたものの、授業数の少ない夜間部では、教員免許・司書免許の両方の単位の履修は難しいとあきらめていた。「自動車運転免許とか秘書検定とか取れるものは取っちゃおうっていう時期だった」勢いにも乗って、2カ月の講義に通い、司書の資格試験に合格する。司書になる人たちが本来学んでいるはずの図書館学・図書館情報学などの勉強は十分ではなかったと振り返るが、このことが、のちに実践のなかで人や本から多くを学ぼうとする姿勢につながった。
1985(昭和60)年、大学4年生で埼玉県の県立高校に配属されることになる。


救っているようで、救われていた
最初に勤めたのは埼玉県立岩槻商業高校(さいたま市岩槻区)だった。図書館は別棟にあってほとんど利用されておらず、本に興味がある生徒も多くはなかった。図書館に生徒と先生を呼ぶために、新着図書やおすすめの本を案内する広報を頻繁に発行し、どんな本が図書館にあるのかが分かるように目録をデータ化した。図書館内の書架や机を動かしてレイアウトを変え、文学全集など重厚なものばかりだった蔵書に、コミックや、当時流行していた『三毛猫ホームズ』シリーズ(赤川次郎著)などを加えた。室内の一角に畳を入れて寝転べるスペースを作って周りにコミックを配置すると、生徒ばかりでなく先生たちにも人気の場所になった。
女優の宮沢りえの写真集『Santa Fe(サンタフェ)』10が発売された時には、生徒たちが「図書館に入れて!」と大騒ぎ。利用者の求める資料は提供したいと思ったものの、図書館の収集方針と照らし合わせてもヌード写真集を入れることは難しく、個人で購入して、生徒と一緒に鑑賞──商業高校にはそんな思い出もある。
先輩司書に誘われて、学校図書館問題研究会11の活動に参加し始めたのは司書になって3年目。1988(昭和63)年に熊本県で行われた全国大会に出席した。この頃は学校図書館も利用者のプライバシー問題に取り組んでいたことから、参加した分科会では、貸出記録や予約をどう管理しているかが議題に挙がった。「予約の受付はどうしていますか」の質問に、積極性を見せたい気持ちもあって「ハイ!」と手を挙げて、ノートで取っている旨を発言、それで、司書として利用者のプライバシーを守ることをどう考えているのか! と集中砲火を浴びた。そうした体験もあって、木下さんは学校図書館司書の仕事についてより深く学び、学びを実践に移していくようになる。
2002(平成14)年に埼玉県立春日部東高校(春日部市)に転勤する。木下さんはこの高校での日々を、「生徒とのつきあい方を学んだ時期」と言う。不登校の生徒を図書館で預かることも経験した。担任の先生や保健室、管理職と情報を共有しながら生徒を支える体験ができたことも大きかったと振り返る。これは、埼玉県が学校司書を、学校と図書館で働く専門職して位置付けているからこそできたことだと言う。今振り返って「相手の領域に入り過ぎていた」と省みるものの、この時は必死だった。
「テスト受けなきゃ進級できないような時には、『なにやってんのよ、頑張らなきゃだめよ』って連れ出して受けさせたりしていました」
プライベートで苦労の重なった時期でもあった。家庭内に厳しい問題を抱える一方で、認知症になったお母さんを介護していた。決して良い思い出ばかりではないお母さんの面倒を見ながら、「親らしいことをしてもらっていないのに」と思うこともあった。家族間の問題、介護のこと……などを本で調べながら苦難に向き合うなかで、生徒たちが抱える問題のことも手に取るように理解できるようになっていた。
「家では自分の存在が苦しかったから、生徒たちのために自分が存在していることに価値があった。その子たちを救っているようで、救われていたんだと思います」
そのぶん、春日部東高校との生徒たちとの関係は深かった。現在までつきあいが続いている卒業生も多く、そのなかに司書になった人もいる。それぞれの道で活躍している卒業生から連絡をもらうと、自身の恩人たちの顔をいくつも思い浮かべ、「恩送りってこういうことなんだな」とふと思うことがあると言う。

埼玉県高校図書館フェスティバルと「みちねこ」
勤務する学校で司書として生徒たちと接する一方で、木下さんは学校図書館の問題、司書の労働環境、そしてそれらに影響される子どもと本の関係に向き合うべく、活動の範囲を広げていく。1989(平成元)年に行われた学図研全国大会で「すべての学校図書館に専任の専門職員を」という大会アピールが出され、それを受けて埼玉県で「学校図書館を考える・さいたまネットワーク」という会が1992年に発足した。これにより、埼玉県では学校図書館の充実に向けて具体的な動きが生まれることになる。これらの活動の中心となっていた司書たちの「次の世代」にいた木下さんは、流れを引き継ぎ発展させていくことを自分の役割と受けとめた。
周囲の学校図書館司書とともに、木下さんは2011年に「埼玉県高校図書館フェスティバル」12を立ち上げた。定期的にシンポジウムを行い、集まったメンバーで学校図書館の課題について話し合うことを通して、学校図書館に専任の司書がいかに必要であるか、図書館の環境が子どもたちにもたらすものがいかに大きいかを社会に訴えかけた。マスコミへの働きかけも積極的に行い、活動の内容は全国紙埼玉版や地元の埼玉新聞にも取り上げられた。そして、2012年には、埼玉県でしばらく行われていなかった司書職採用試験が再開されることになる。
木下さんは活動の広報にあたって、関心を持つ人や媒体があればすぐに出向き、必要とあればマスコミ・報道関係者の前にも積極的に出ていった。この活動の軌跡や学校図書館の現状・活用法について書かれた著書『読みたい心に火をつけろ!』13発刊の際には、木下さんを模した(?)挿絵キャラクター「みちねこ」が誕生し、活動の普及に一役買った。みちねこのコスチュームもあり、それは書店でのイベントやラジオ出演14時などに活躍する。「埼玉県高校図書館フェスティバル」の活動は、現在も「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本」の取り組みとして引き継がれている。
本と木下さんを引きあわせ、社交的な性格と行動力とを木下さんに授けたお母さんは、2015年に他界した。お母さんが仕事でお世話になった人々に知らせたところ、何人かが弔問に駆けつけた。訪れた人の話から、娘の立場からは見えなかったお母さんの一面を知った。職場にいる時、自分のことをいつも気にかけていたことも聞いた。愛憎入り混じる思いのあった人のことを、木下さんはいま穏やかに思い返すことができる。

創造力を支え、生きる力を支えるために
現在、木下さんは、県内有数の進学校である埼玉県立浦和第一女子高等学校(さいたま市浦和区)に勤めている。これまでと同じように、新着図書を知らせる広報を積極的に発刊する一方で、教科との連携を密接にするために先生たちとのコミュニケーションを重ね、学校図書館がより生徒たちの近くに存在できるように努力を重ねている。埼玉県立春日部女子高校(春日部市)勤務時に初めて取り組んだビブリオバトル15も、さらに活発化させている。2014年に設立された「高校生直木賞」16にも、生徒たちとともに参加した。その活発な活動内容と人柄から、県を飛び越えて各地から講演会に呼ばれている。その動きのなかでたくさんの学校図書館と手をつなぎ、たくさんの司書との結びつきを深めている。
さまざまな事情から生きていくことが困難な子どもたちに対して、学校図書館の役割は大きい。本が身近でない環境に育っても、幼稚園・保育園に通っていれば、読み聞かせてもらう機会はある。しかし小学校に入学すると、個人によってその機会に大きな差が出る。「だから学校図書館の出番なんです」と木下さんは話す。
「日本は高度成長期があったから、私たちが子どもだった時代までは、誰でも努力すれば向上できるという理論が成立していました。お金を稼いで裕福になるのは努力している人、というのは事実だった。そして、小さなコミュニティ……家族やご近所さんや会社が優しくて、手を差し伸べる成功者が具体的に存在して、助けられた側も真面目に働こうとしていた。力を借りて貧困から抜け出そうという意識がありました。でもいま、貧しくて困っている人の状況は、ふつうの人の想像以上に酷いものです。親が小さい子どものために自分の空腹を我慢できない、スマートフォンを手放せない、夜遊びに行くことをやめられない。どうすれば現状から抜け出せるかと道すじを考える創造力を持つことができない。だから社会全体で支えなければ」。
子ども食堂などの動きによって社会が子どもの貧困と向き合うなかで、木下さんは「自分で読めて、調べて、考えることができる子を作らなければ変わらない」と考えている。
「おにぎりを食べておなかが満たされたら、知的なことを身につけなければいけない。それが次のポイントだと思うんです。川口市の事件の彼は、知を求める力を持っていた。生きていくために教育が必要だと思える想像力があった。だから彼はこれからも生きていくし、人のために動いていくでしょう。それが彼の役割だと思うんです」
木下さん自身、かならずしも恵まれてはいなかった子ども時代を、今日を生きる子どもたちに重ねる。だからこそ生まれてくる力もある。
「どうして自分がこんな思いをしなくちゃいけないんだろうって思ったら、変わりたいって思うじゃない。そこからがスタート。でも虐待されている子は、小さすぎて分からない。今の何がダメなのか、どう変わりたいのか。それを考えるチャンスがないまま大人になっちゃうじゃない。それを考えるのが創造力で、創造力を授けてくれるのは本だと思うんです。人は、ずっと続くつながりもあるけれど、裏切ったりいなくなったりすることもある。でも本はずっとそばにいる」
本を読めない子が読めるように、読書が苦手な子にその喜びを伝えられるように──人は誰しも役割を与えられて生まれてきた。だとすれば、と木下さんは言う。それを見つけられずに人生を終える人がたくさんいるなかで、自分の役割、自分が人様のために何ができるかを考えて見つけることのできた自分は幸運だと。