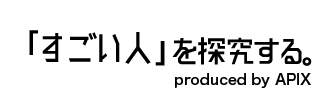初めて行っても不思議とくつろげる店がある。小さな空間のなかで、店主と適度に会話を交わしながら、タイミングよく供される美味しい料理とお酒をゆっくりと楽しむ。とりとめもない話なんだけど心地良い。周りのお客さんも、適度な距離で時々話に加わる。笑い声が店内に響く。気がつけば入店から3時間くらい経っている。コース料理の締めの食事も終え、温かい気持ちで店を後にする。
──「和食 久野」を簡潔に表現すれば、そんな感じの店になる。
JR総武線・平井駅1から徒歩1分。駅前にある巨大マンションの裏側の1階、人通りの少ない場所にひっそりと佇む。駅に近い至便な地にありながら、誰かに教えてもらわなければなかなか辿り着けない。カウンター8席のみというこの小さな店には、お客さんにとっての居心地の良さを究極までに追求する店主・久野恭敬さんの、強い想いが込められている
。
異色の経歴
1968(昭和43)年、愛知県東海市2で生まれた久野さんは、大手食品メーカーに勤める父上の転勤もあって、幼い頃から京都、大阪、福岡、仙台、東京など全国を転々とする。料理上手の母上の手伝いをよくしていた3という少年は、剣道と水泳に打ち込む日々を過ごすなかで成長し、大学時代は体育会ヨット部で心身共に鍛えられる。
その後の経歴は異色と言ってもいいだろう。大学卒業後、証券会社に勤務した後、11年間に及ぶ料理人としての修業を経て、「和食 久野」を立ち上げることになる。
「なぜ私がいまの道に入ったかというと、大学時代にヨット部を指導してくれた監督4のお陰なんです。当時は証券会社に入社して2、3年が経ち、何かしらの商売で独立を考えていたものの、自分が何を目指せばいいのか迷っていた。たまたまお宅にお邪魔して監督と話をしているうちに、飲食をやってみたいな、と思うようになっていった」(久野さん)
監督の実家がマグロ卸業を営んでおり、多くの飲食店と仕事をしていた。久野さん自身、母の影響もあってもともと料理を作ることは得意だった。問題は、すでに27歳になっていたにもかかわらず修業経験がないことであった。マグロ卸業の取引先の一つ、水道橋にある寿司店を修業先として紹介してもらい、ゼロからのスタートを切ることを決意する。
入門の早さで有利・不利が決まるのが職人の世界だとすれば、久野さんは大きなハンデを背負っての挑戦と言える。しかし、一見遠回りに見える“経歴”であっても、そこでの経験がすべて血肉と化していけば話は変わってくる。この道一筋の料理職人とは違った“個性”や“スキル”を身につけることができるからである。

11年間の修業
修業先の親方は、証券会社に勤務したのちに独立した人で、久野さんが目指す道を行く先輩でもあった。店は30人弱のお客さんが入れる規模で、親方と女将さん、息子さんのほか、若い衆が3人ほど働いていた。
「丁稚奉公するつもりで飛び込みました。結婚を目前に控えていたこともあり、とにかくこの世界で一人前になることだけを考えていた」
1年間は給料なしでお願いします、という久野さんの申し出に対し、親方は、「気持ちはわかるが、そういうわけにはいかない。おまえはもうすぐ家庭を持つんだしな。その代わり、4年間で一人前に仕上げてやるから、そのつもりで頑張れ」と発破をかけた。
この言葉は愛情の裏返しを意味したが、実際の修業は想像以上に厳しかった。朝は5時半に起床し、買い出しの手伝いや掃除、そして仕込みに追われる。夜は後片づけで仕事が遅くまで及ぶ日が続く。その間、親方からの容赦ない厳しい直接指導も加わった。
「涙が出るような修業で、毎日がつらかった。実際に何度も泣いた覚えがある。でも、彼女(=婚約者)の親父さんに『一人前になって必ず自分の店を出す』と啖呵を切った手前、泣き言を言っている場合じゃあなかった」
結局、5年間の修業に耐え、寿司職人として一本立ちできるまでに成長する。だが、久野さんの修業はここで終わらない。寿司だけでなく、和食の技術も身につけたいと考えたからである。再び監督の紹介により、恵比寿にある日本料理店で修業の第2ラウンドが幕を開ける。煮物や焼き物、揚げ物からお椀ものなどまで、和食の基本をどん欲に学び続けた。前の店で教わったふぐ料理についても、修業の合間を利用して講習に通いながら勉強し、ふぐ調理師免許試験に一発で合格する。ふぐ料理が楽しめる店を、というのは、奥さんと交わした約束でもあった。
こうして日本料理店での6年を加えた11年間に及ぶ修業を終え、独立する手筈を整える。2006(平成18)年春、久野さんは38歳となり、すでに2人の娘さんもいた。

平井との縁
恵比寿の日本料理店を辞める日の1週間ほど前、現在借りている平井の店舗物件に関する話が久野さんの耳に入る。義父上が仕事の関係でよく飲みに行っていた小料理店で、着物姿の女将さんが一人で切り盛りしていたものの、高齢を理由に辞めるという。料理店で修業中の娘婿がいずれは独立を考えているんだ──義父がもらした話を覚えていた女将さんが、「自分の後にどうですか」と言ってくれたのだった。
久野さんにとって平井はまったく未知の土地だったが、本格的に店探しを始めようと思っていた矢先に届いた朗報であった。義父と奥さん、そしてまだ小さかった娘さん2人とともに、自分の目でどんな店かを確かめに行くことになる。
実は平井の話が出る2年ほど前、久野さんは出店資金を工面して独立する準備を具体的に進めていたことがある。
「その時は30、40人のお客さんが入れる店を作ろうと考えていました。女房に手伝ってもらうほか、従業員も雇ってね。うまくいけば支店も出したい、とオーナー気取りの夢も描いていました」
すべてを計画書に落とし込んだうえで、名古屋にいる父のところに相談に行った。
「計画書を見た親父からは、『こんな店をやればお前らはきっと崩壊するぞ。計画では毎日満席になっているけど、最初から満席になんてなるわけがない。1年ぐらいはお客さんなんてつかないぞ』と言われ、頭ごなしに反対されました」
喧々諤々の言い争いが夜中の3時頃まで続いたものの、結局父からの許しは下りなかった。翌朝、久野さんが新幹線に乗って帰京すると、父が自宅の庭で倒れたという報せが届く。言い争った時に興奮しすぎたことが原因であった。
「私のせいで親父が倒れた。これはもう完全に自分の責任だった。おれのせいで、と思うと涙が出た」
幸い発見が早かったため命に別状はなかった。独立するには時がある、いまはその時ではないということを、久野さんは肝に銘じた。
それから2年後、この苦い体験を頭の中で蘇えらせながら、平井の店を自分の目で確かめた久野さんは、「この店ならばなんとかできそうだ。初期投資も少なくて済む。最悪駄目だった場合でも、頑張ればなんとかやり直しもきくだろう」と思った。
義父が「やれますよ、あの店だったら大丈夫じゃないですか」と、久野さんの両親に伝えてくれたこともあり、話はとんとん拍子で進むことになる。

石の上にも3年
2006(平成18)年5月1日、久野さんにとって待望のオーナー店「和食 久野」がオープンした。
「店は基本的に居抜きで使ったけど、カウンターと椅子以外はすべて取っ払い、内装も全面的にやり直した。『なるべくシンプルかつシャープにしてほしい』とお願いしました」
木目を生かしたカウンター、白い壁とクリーム色の調度品で統一された店内は、清潔感に溢れ、落ち着きのある空間が広がる。店頭(外)には「和食・ふぐ料理 久野」の看板、義父の筆5による「久野」の行灯、同じく義父から贈られた故事成語の色紙、そしてコース料理の案内が並ぶ。ほどよい音量のジャズ6がBGMとしてゆったりと流れるお洒落な店に仕上がった。
11年間にわたる修業を経て、寿司、和食、ふぐ料理の腕を身につけた。店も、欲張らず一人で切り盛りするにはちょうどよい規模であった。誰の目にも満を持してのスタートにみえた。ところが現実は厳しかった。お客さんになかなか来てもらえず、赤字が増え続けることになる。
「マンションの裏手という立地も災いした。表通りなら新しい店ができれば人目につくんだけど、誰も歩かない場所だからね。近くのビルやマンションに宣伝のビラを蒔いたり、いろいろと努力してみたけど、お客さんは想像以上に来ませんでした」
義父をはじめとする身内や友人・知人が知り合い等を誘って繰り返し来店してくれたものの、それだけでは限界があった。3日間一人の客も来ない時も何度か経験したという。開店してから2年目に入っても、食べていけない状況が続く。次第に焦りが募り始め、精神的なストレスを抱えていくなか、久野さんにさらなる災いが追い打ちをかける。奥さんが大病を患い、入院したのである。
店が終わったら病院へ行き、入院中の奥さんに付き添い、そこでいくらかの仮眠をとって翌朝河岸に出かける、という毎日が1カ月半ほど続いた。
「ああこれはもう駄目だな、辞めようと思った」
弱気になった久野さんのもとに、周りの人たちが必死になって応援に駆けつける。奥さんの家族、自分の両親も姉弟たちも、交替で娘さんたちの面倒を見てくれたり、奥さんの看病をしてくれたり、家事を手伝ってくれたりした。親身になってくれる常連のお客さんにも恵まれた。30枚ほどの店の名刺を、自分の知り合いに配って回ってくれたという。
「あの頃はいちばんつらかった。でも、たくさんの人たちの想いを考えたら、負けるわけにはいかなかった。あの時のことを思えば、そうそうつらいことはない。健康でさえいられれば、売上げがないとか、3日間お客さんが来ないとかは、もう耐えられるようになった」
せっかくここまで頑張ってきたんだからあきらめるな──という周囲の励ましの声を力にして、久野さんは初心に戻ってそれまで以上に真摯に仕事と向き合った。
そして、こうした姿勢に応えてくれるかのように、奥さんの病状は回復へと向かい、お客さんも徐々にではあるが増え始める。開店3周年を迎える2009年春になると、店は目に見えて賑わうようになってくる。「石の上にも3年」という言葉どおり、どん底の苦しみを乗り越えたことで、経営は次第に軌道に乗っていった。

究極の“居心地の良さ”を
そもそも久野さんが目指した店とは、いったいどんな店だったのだろうか──。
「勉強のために高級店にもいろいろと出かけてみることがあります。緊張感のあるなかで美味しいものを静かに食べるのもいいけど、私はあんまり好きじゃなかった。もっと気さくに会話を交わしながら料理やお酒を楽しめる、知らない者同士でも、楽しい空間を共有できる居心地の良い雰囲気の店。それがやりたくてこの世界に入ったのかもしれません」
それゆえに、お客さんと接するうえで最も大切にしていることは、「誠意をもって、楽しく気持ち良く」だと言う。そのために、常連のお客さんはもちろん、新しいお客さんについても、一人ひとりの特徴を頭に入れたうえでノートに記録する習慣を続けている。
「いまは何を召し上がったかまでは書ききれないけど、昔はそこまでやっていました。何が苦手だったかも記録につけて覚えています。例えば、『柚子は苦手でしたよね』などと言って他のお客さんと違うかたちで料理を出すと、お客さんは『えっ、4、5年も前のことなのに』と驚きながら喜んでくれるんです」
ちなみに筆者の連れが初訪問した際、酒に強くないことがわかると、2回目以降、酒類を注文するたびに必ず、「(生ビールは)グラスがいいですよね」「(ウーロンハイは)焼酎薄めがよかったですよね」と、言われなくとも的確に対応してくれる。すべてが頭に入っていることに驚駭(きょうがい)した覚えがある。
久野さんが接客でもう一つ大切にしているのは、「話の共通項」を見出すことだと言う。
「何かしら共通点があると、人って打ち解けられるんです。海外で日本人に会うと親近感がわくようにね。出身地でも出身校でも趣味でもなんでもいいから、共通項になるものをちょっと投げかけると、会話にもつながるし、すごい親近感が生まれる」
ほとんど毎日予約で席が埋まることを生かして、お客さんの席の配置にも心を配る。
「なんとなく常連客が多い店だから、お客さん相互の相性というのもわかっている。カウンター8席のなかでも、相性を考えながら割り振りを頭の中で考えて席の配置を決めています」
例えば、ゴルフをやるお客さんが重なれば、隣同士に座ってもらい、ゴルフの話題を振ってみる。無理やりくっつけようとするわけではなく、自然の話の流れのなかで、「あっ、ゴルフやられているんですか」と隣のお客さんが話の輪に加わったりする。
「私は親父の転勤でいろいろな街を渡り歩いてきました。また、証券マンとしての経験7を通じて、物怖じしなくなったし、トーク術のようなものも自然に磨かれてきた。いろいろな“寄り道の人生”が、どこかでいまの仕事に活かせているのかもしれませんね」
絶妙の距離感を保ちながら、ごく自然にお客さんにとっての居心地の良さ、楽しい雰囲気づくりを演出する久野さんであるが、最初からそれができたわけではない。開店当初は、お客さんに気に入られようと、店が終わった後も付き合いで飲み歩く毎日だったという。
「本当に知らない土地に飛び込んできたから必死でした。だからお客さんとくっつきすぎていた。“男芸者”じゃないけど、とにかく気に入ってもらうことだけを考えて、何でもやった。でも、しばらくするうちに、自分のやりたいことがどんどん遠ざかる現実に気がついて、途中で辞めましたね」
新しいお客さんが来てくれても、常連とだけしゃべっていたらいい気分はしない。久野さんは、こうした教訓を胸に、初めて来店するお客さんを、楽しく気持ち良く迎えることに最も腐心するようになる。常連客もそうした姿勢を理解して、逆に楽しい雰囲気づくりに協力してくれるという。

料理人としての矜持
11年間に及ぶ修業、寿司職人としての基本やふぐ調理師免許の取得は、本格的な料理で勝負できる店を目指したためである。それゆえに、料理に対するこだわりも強い。
「料理に関して言えば、自分が100%美味しいと思えないものは出さない。店が暇になると食材が余ることもある。でも、『これはギリギリいけるな』などと考えたことは一度もない。自宅に持ち帰って、煮たり焼いたりするなど火を入れて食べることはもちろんあるけど、お客さんには100%自信のあるもの以外、決して出さない。これだけは守り続けている」
こうした考え方は料理人であれば当たり前に聞こえるかもしれないが、実際には経営が苦しくなると基準を甘くする店も少なくない。料理人としての矜持とも言える久野さんの姿勢は、身近に“師匠”がいることも影響している。名古屋で園芸業を営む伯父上の存在である。
「蘭の大家でテレビにもよく出ていた人ですけど、生花市場で花を売っていた昔からいまに至るまで、少しでも怪しいと思った生花はすべて『悔しいけど捨てた』って言うんですよね。私が店を開く時、『それをおまえもやるんだぞ』とアドバイスしてくれた」
万が一この約束を破るくらいなら、店をたたんだほうがいい、と久野さんは断言する。
もう一つのこだわりは、「おまかせコース」にある。開店当初からメニューとして「ふぐコース」「寿司コース」はあったものの、平井という下町気質が色濃い場所柄、単品注文のお客さんがほとんどを占めていた。
「どうしても居酒屋使いになってしまっていました。お通しとお酒だけで3時間くらい滞在するお客さんもいた。もちろん、居心地良く過ごしてもらうため、話し相手にもなる。ただ、しばらくやっていくうちに、自分がやりたいことはやっぱりこれじゃないな、と思うようになりました」
2、3年経った頃から、「おまかせコース」を新たに加え、コース料理を基本とする方針に切り替えた。そこには、久野さんのスペシャリティとも呼べる料理8も季節ごとに並ぶ。「おまかせコース」にすれば、仕入れのロスも少なくて済むうえ、その時々の旬の食材をためらいなく生かすこともできる。結果として、お客さんにより満足してもらえる料理を廉価で提供することになる。いまでは、ほぼ7割のお客さんがコース料理を注文してくれているという。
「お酒を飲めない女性のお客さんも増えており、2時間くらいかけて、お茶を飲みながらコース料理を楽しんでくれる。徐々にですが、自分の理想とする方向へ近づいています」


職人冥利、そして夢
「和食 久野」が開店してから13年近くの月日が流れた。
「店を続けてきて感じるのは、カッコいいことを言うようだけど、『人との縁』に尽きますね。そして、うちの場合はその縁が怖いくらいにつながる。周りの人たちのつながりもそうだし、いいお客さんがいいお客さんを紹介してくれることも本当に多い」
だからこそ、質の高い美味しい料理を出し続けなければいけない9。お客さんに楽しく過ごしてもらわないといけない。誰一人として、裏切ることはできない。「(このことが)13年近く続けてこられた秘訣かもしれない」と、久野さんは付け加える。
お客さんの年齢層も幅広く、30代の若い女性客が多い点もこの店の特徴と言える。一方で、高齢の常連客も少なくない。喜寿や傘寿、米寿のお祝いに家族で来店するお客さんもいる。当然のことながら、亡くなられるお客さんも出てくる。そのなかには、“最後の晩餐”として久野さんの店を選ぶケースもあるという。
「ありがたいことに、最後の晩餐を久野ちゃんで食べたい、というお客さんが4、5組ありました。病気ですでに痩せ細っていて、車椅子で来られる方もいらっしゃる。皆さん、もうほとんど食べることもできない。それでも、口をつけてくれる。そして、満足した表情で店を後にされる。しばらくしてご家族から、『ありがとう』という感謝の言葉を添えて訃報の報せが届く。身体がつらいなか、この店に何か楽しい想い出があるからこそ選んで来てくれた──そう思うと、これはもう本当に職人冥利に尽きますね」
今春、久野さんの2人の娘さんが揃って高校と大学へと進学した。これを機に、店に自転車でも来られる場所に自宅を引っ越すことも決まった。奥さんの子育てが一段落してくれば、長年の夢であった二人で店を切り盛りする日も遠くない。
「いまのようなカウンター席に加えて、8席程度のテーブル席があって、そこで会社関係のお客さんたちがちょっとした打ち合わせをして、終わったらみんなで『ご苦労さま』と言いながら一杯やれる──そんな店ができれば理想です。そのためにはもう一人、ホール兼会計係が必要になる。それを女房がやってくれればね」
久野さんは数年前から、この理想の店舗物件を探し始めている。縁がさらなる縁を呼ぶ店だけに、この夢が叶う日は意外と早くやってくるに違いない。