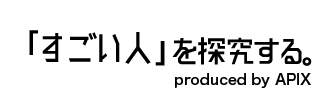「ほとんど毎日、外の本棚を見に来てくださるお客様がいるんです。必ず買ってくださるわけではないんですけれども、新しく入れた本をその日のうちに買っていかれたり、値下げした途端に買われていかれたり。僕よりもよっぽど、外の棚については頭に入ってらっしゃるんじゃないかな。また先ほどいらっしゃった方も、3日に1回くらい、ずっと外の棚の本を買ってくださっている常連です。年間にすればものすごい量ですよね。とてもありがたいし、嬉しいです」
劇場を中心に、古着店やカフェなどが集まり、若者文化の発信地である「下北沢の中心部」(店頭窓ガラスに赤い文字で大書されている)にある「古書ビビビ」。淡々と話し続けていた店主・馬場幸治さんの顔が、この話をするときにはとても優しくなった。
一般に、古書店の店舗前にある本棚は、店舗内の本に比べて割安の本で埋められる。価格は元の値段にかかわらず100~500円ぐらいまでのいわばバーゲン品であり、店によっては“売れ残り”的なニュアンスもあったりする場所である。
しかし、古書ビビビの店頭本棚は、マンガやマイナーでオフビートな面白本、映画・演劇から思想書まで、サブカルチャーを中心とする文化芸術系で分厚い品揃えを誇る下北沢の個性派古書店らしさを存分に出している。「あっ古本屋さんだ」とはしゃぐ若者から、上記のような渋い本好きまでを引き寄せるラインアップがそこにある。しかも、その半分以上は、ガラス扉付きの本棚に収められていて、たたき売りされている感じがしない。古書ビビビの店頭は、馬場さんの本や古書店に対する想い、姿勢、そして軌跡までを示す、豊かな表情をもっている。
バイト店長として武者修行
1976(昭和51)年に東京の狛江市で生まれた馬場さんは、とりたてて読書少年だったわけではない。
小中学校時代は、怪奇モノや妖怪モノを人よりちょっと多く読んでいたぐらいで、あとはSFやミステリなど、男の子が好きな本を人並みに読んでいた1。お小遣いの使いみちも、ゲームソフトなども欲しかったため、本については中古を安く、うまく買うのが大事だった。中学校時代には、近所にある総合リサイクル店の一角にあった1冊50円の文庫本コーナーで、星新一や江戸川乱歩などを探し、読み終わったら次を買うのが楽しみだった。
本格的に本の世界にのめり込み始めたのは高校時代からで、スティーブン・キング2を読みまくり、さらにSFや幻想文学へと徐々に範囲が広がっていった。ほぼ同時期に、マンガの稀覯(きこう)本収集にはまったことが、「本の世界」との関わりを一気に濃くした。知らない街へ行って古書店を巡るのが趣味になり、「宝さがし」の感覚が加わる。
その後、大学に進学した馬場さんは、現在の自分につながる経験を積む。
馬場さんの趣味を知る友人から、「調布のマンガの古本屋で珍しい本を売ってたよ」と聞き、足を運んだ。その書店では、手塚治虫や藤子不二雄のレア本がショーケースに収められており、店長からも絶版本やその探し方などを教わって、収集が加速する。知識が増えたことで、収集と一緒に「せどり(競取り)」3もできるようになった。
さらに同書店に通い詰めてしばらくしたころ、店長が店を辞めることになった。居合わせたオーナーから、「君、よく来てるしマンガに詳しそうだから、店長やらない?」と言われたことで、馬場さんの店舗運営の第一歩が始まる。
この時、馬場さんは20歳前後、もちろん、まだ大学生だったため、アルバイト店長の誕生である。この「バイト店長」生活で、古書店経営の基本を身に付けることができた。もちろん、この間、趣味の古書店通いも続けている。

「自分の店」へ古書店巡りを精力的に
バイト店長を5~6年続けたのち、馬場さんは自分の店をもちたいとの気持ちが強くなり、独立に向けて動きだした。大学を卒業し、腰を据えて進路を定める時期になっていた。
自分で古書店を開業するという馬場さんに、両親はことさら反対もしなかったが、特に父親は落胆を隠さなかったという。馬場さんの実家は理髪店を経営しており、跡を継ぐことを期待されていたからである。実際に馬場さんも、大学と並行して夏と冬には理容専門学校の短期講習に通っており、理容師資格も取得していたが、本の世界で生きることを決めた。
自分の店を創ることを決めてから、馬場さんは以前にも増して古書店を集中的に回った。ひとつは店づくりの参考にするため、もうひとつは少しでも多くの「本の背」を頭に叩き込むためである。マンガについての知識には自信があったが、新しく開く自分の店ではお客様の間口を広げる意味でもう少し幅広いジャンルの本を置きたかったし、買取もマンガだけ、というわけにはいかない。お客様と話をし、関係を深めるのに「知識」が大切なことは、店長としても、古書店の客としても体験的にわかっていた。
雰囲気や品揃えが好きで取り入れたいと思った店のひとつは、高円寺にあった「ZQ(ジーキュー)」4。もうひとつは、経堂の農大通りにある「大河堂書店」5である。

下北沢「すずなり横丁」で
店づくりのイメージは固まってきたが、肝心の店舗はなかなか見つからなかった。神保町や世田谷の三宿あたりで物色したが、いい物件がない。たまたま散歩していてテナント募集の貼り紙を見つけたのが、初代の店舗であった。現在の店舗からすぐ近く、本多劇場と並ぶ下北沢の演劇のメッカである「ザ・スズナリ」61階にある「すずなり横丁」の一角である。同横丁にはスナックやバーが並んでいて昼は少し薄暗く、当時はおよそ物販をやろうという人はいない空間だった。しかし、7坪足らずの小ぢんまりとしたスペースで最初に揃える本の数が少なくて済むこと、ゆくゆくは“一杯飲める本屋”を経営したいと考えていたこと、さらに当時は喫茶店を併設するミニシアター「シネマ下北沢」7が隣に、近所には評判の雑貨店もあって、演劇・映画ファンや女性にも来客してもらえること――などから、馬場さんはここで開店することを決めた。
こうして2005(平成17)年1月、馬場さんの店がオープンした。店名の「古書ビビビ」は、「身体に電流の走るような刺激的な出会いを提供したい」という意気込みからつけた8。馬場さんは、自分なりの個性を出すとともに、勢いのあったブックオフなど新古書店チェーンの良いところは素直に取り入れている。
「マンガだけのマニアックな古書店と思われるのは嫌だったし9、商売的にも入り口は広くしておいたほうがいいと思っていました。入りやすくて明るく、できるだけきれいな本を安く出すことで気軽に買えるようにする、というブックオフのノウハウなんかはちゃんと勉強して参考にしています10。店自体も明るい雰囲気にするため、扉を新品に替えたりしましたが、実際にはちょっと覗いて恐れをなして帰っちゃうお客様もいました(笑)。当時は『ありふれた本は置かない』ということを今より強くアピールしていましたし」
〝ありふれた本は置かない〟のは、店の個性づくりであると同時に、ビジネス上の要請からでもあった。ベストセラーの古書を置いても、好立地の新古書チェーン店とは勝負にならないからである。

お客様との関係がすべて
こうして開店した古書ビビビは、常連客を順調に増やしていった。
馬場さん曰く、「ここでなく他の街だったらもう店やっていないかも、ぐらい僕にはとても合っている」下北沢という土地柄が後押ししたことに加え、現店舗に移ってからも変わらない、話しかけやすい雰囲気をできるだけつくる努力という馬場さんの姿勢も大きい。
「お客様との関係がすべてというところがありますから」
この言葉には、できるだけ多くの幅広いお客様に、面白い本と出会ってもらう場としての店を、という馬場さんの考えだけでなく、仕入れ面でのお客様の存在が大きい古書店ならではの事情も込められている。
「本を買い取っていくには勉強しなければなりませんから、サブカルチャー的なジャンル以外でも面白い本はたくさんあるということがわかってきましたし、そういった本も扱えるようにしたいと思うようになりました。今も勉強は続いています」
馬場さんのお客様との関係は、古書組合11に加盟していないという点にも表れている。
「別にポリシーがあってという訳ではなく、最初はお金がなかったこと、今は単純に時間がないのがいちばん大きな理由です。バイトを使えば時間はできるのでしょうが、うちは奥さんと2人でやっていますし、店で買い取った本の整理だけで手一杯なので」
古書組合の加盟には、買い取った本のうち、自分の店に合わない本を市場に出すことで整理しつつ収入を得るというメリットもあるが、これも古書ビビビでは必要なかった。
「買取の希望があった場合、一山いくらということではなく、引き取れない本も含めて1冊ずつ説明して、納得してもらうようにしています。引き取れない本は、『〇〇のほうが高く買ってもらえますよ』『図書館に寄贈しては』とできるだけ別の売先・譲渡先も紹介・提案します。出張買取の場合も、お客様には少し煩わしいかもしれませんが、事前に電話でラインナップを細かく聞いて同様にしています」12

面積数倍の現店舗へ移転
開店から5年ほどが経ち、買取が増えるとともに、店舗は徐々に手狭になっていった。あらゆる空間に本を詰め込んでも溢れ、自宅に持ち帰る状況になる。現在もメタルラック数本が埋まり、押し入れに詰め込んだ稀覯マンガ本のコレクション200~300冊も含めて、2000冊余の本があるという。
また、前述のようにサブカル以外の分野、小説や思想、心理学などの分野も徐々に買取が増え、馬場さん自身もこれらについて勉強していくなかで、扱うジャンルや冊数を増やしたいという気持ちも大きくなった。どこかもっと広いところへ移ろうと考えるなかで、現店舗のスペースが空く。元の店舗から数十メートル、本も現在ほど多くなかったので、引越しは台車を使って済ませられた。
「現店舗は格段に入りやすくなったので、とても嬉しかったです。もちろん、家賃は高いので、必死で売らなくてはいけないですけれども。飲食店と違って、爆発的人気を呼ぶということもないし、たくさん売れるわけでもないので、古書店を続けるのは大変です。ネットから出発して実店舗を設けたもののネットに戻ってしまう古書店は少なくないですし」

文化発信と小出版社の支援
馬場さんは古書販売に加え、出版やイベント開催などにも積極的に取り組んできた。最初に始めたのは、レア本のデータベース化やマイナーなマンガ本の再出版である。
「とても面白いのに、ほとんど知られていないマンガ本を何とか多くの人に読んで欲しいと思って。調べてみるとそれほど費用もかからないことがわかったので、漫画家さんに相談を持ちかけてこぎつけました。4冊くらい出しています13」
また、古書店としては広い現店舗に移ってからは、イベントが実現可能になった。現在もレジの後ろに掲げられているカメラマン・川島小鳥さんの代表作「未来ちゃん」の大パネルは、写真集出版時に古書ビビビで開催した写真展終了後にもらった。14
「壁以外の本棚にはすべてキャスターをつけて、スペースがつくれるようにしたので、地元ミュージシャンのミニコンサートやアイドルのサイン会もできるようになりました」
もうひとつ、古書ビビビが行っているのが小出版社の新刊販売である。
「現在置いている夏葉社さんは、同社が2冊目として出した『昔日の客』15という本がすごくよくて。扱いたいなと思っていた時に、出張買取に行ったお客様が夏葉社さんと知り合いで、『紹介してあげるよ』と言ってくれて、以降、全ての出版本を置いています。大きな出版社の本は、いくらでも扱ってもらえるでしょうから、小規模出版社を応援していきたいと思います」

本は100円でも宝物がある
馬場さんは、店舗を開く前にネット販売を先行したり、カード決済を取り入れるなど、ネットや電子サービスの利用に躊躇はしない。本と対抗するイメージで語られがちなネットだが、“読書”にしても、情報だけ得ればいい本や青空文庫などネットならではの発信機能を活かすサービスであれば、デジタルでも構わないともいう。
「でも手触りやめくっていく感覚などを含めれば、モノとしての本がやっぱりいちばんいいと思うんです。お客さんと話もできますし」
そして、古書の良さも、現物としての本に負うところが多いはず、とも力説。
「安い本はものすごく安いですけれども、安いからといってつまらないわけではないじゃないですか。100円で本当にいい本にめぐりあえることもある。映画と比べても安く時間をつぶせて、さらに人生が変わるぐらいのインパクトを受けたり、世界が広がったりします。店頭に気になる本があったらまず買ってもらいたいですし、そのためにもできるだけ安く出したい」
個性派古書店としてカラーを出しながら、売り買いの両面でお客様との関係の基本――しっかりした値段で買取り、できるだけいい状態の本をできるだけ安く出す――をゆるがせにしない古書ビビビのカウンターには、かつて50円で面白い本に出会い、店長との会話で知識を広げ、宝さがしに胸を躍らせた馬場さんが今もいる。