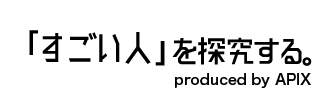風俗店で働く女性たちのあいだで、たびたび話題になった若いライターがいた。お店やスタッフがメディアの取材を受けると「載せてあげるんだから」と金銭を催促されたり、取材にかこつけてプレイを要求されたりすることは、悪習ではあるがまかり通っていた。でも、男性向け風俗情報誌の取材に訪れた彼はそのどちらも求めなかった。
質問する内容も変わっていた。“風俗嬢”としてではなくひとりの女の子としての横顔を知ろうとする質問——たとえば「マクドナルドでいつも何食べるんですか」というような——を、いくつも投げかけた。彼女たちは「えっ、なんでそんなこと聞くんですか」と笑うこともあったけれどきちんと質問に答え、彼はそれらをもとに原稿を書いた。
彼女たちのふだんの表情が掲載された記事は、お店にたくさんのお客さんを呼び込むことになる。女の子たちと同世代の彼のことを多くの風俗店は信頼したし、「また来てほしい」「また書いてほしい」と望んだ。
雪の町に育ったサッカー少年
編集者・川越敬志さんは、1960(昭和35)年に新潟県長岡市で生まれた。冬になると雪に降りこめられる町でサッカー少年として育った川越さんには、文学少年の顔もあった。雪深い時期は外に出ることもままならず、本を読んで過ごすしかなかった。甘い両親ではなかったけれど、本だけは欲しいものをすべて買ってもらえた。会社を経営していたお父さんの好きだった歴史小説や社会科学系の本も手当たり次第に読んだ。
「それでも結局はサッカーばっかりだし、田舎だから書店に置いてある本も限られていて、かといって図書館に行くってガラでもなかった。だから、慶應の文学研究会(サークル)に入って周りを見て、あまりに自分が読んでいないことに驚いた」
本を作る仕事に具体的にかかわったのは、三田キャンパスの近くにあった編集プロダクションでアルバイトしたのが始まりだった。
「編集の仕事のなかで結局いちばん時間がかかるのは原稿書きでしょう。それがやれる人間が必要だったみたいです。文章に自信はあったけれど、それよりも22やそこらでなんでもハイ、ハイ、ってやる若者がいれば使う。便利だったと思いますよ」
編集プロダクションは、週刊誌の編集制作を複数請け負っており、川越さんはこのうち『週刊チャンネル』1(日本文芸社)の数ページを任されることになる。アポ取り、取材、写真撮影、原稿作成、レイアウトといった一連の仕事をほぼひとりでこなした。冒頭の風俗店取材はこの時のことである。

「器用」なライター
数か月後、アルバイト先で仕事を請け負っていた日本文芸社2の編集者が川越さんの書いた原稿を読んで本人に声をかけた。仕事の状況や待遇のことを話すと、「フリーになったほうがいい」とアドバイスされ、川越さんは大学に籍を置いたままフリーランスライターとして仕事を始めた。この時点で、将来像は具体的に描いていなかった。
「会社員になれば、20年後というのは多少なりとも見える。でもフリーランスとしてスタートしたから、そんな先のことは見えなかったし、見ようともしていなかった」
数年のあいだ、仕事が途切れることはなかった。朝起きて原稿を書き始め、夜までほとんど外出せずに書き続ける。大学はこの時期に中退した。まともに睡眠が取れないことも珍しくはなかった。当時、ライターに対して編集者が原稿を催促する方法は電話以外になく、その電話を川越さんが「留守」に設定していたため、神楽坂の自宅には編集者がしょっちゅう訪れた。ライターとして生活していくために、来る仕事を拒むことはなかった。どのような分野の原稿でどのようなタッチを求められても、できる限り応えた。
「器用だったと自分でも思うし、専業ライターとしてそういう対応は生きるための術でもあった」
そういう生活を約3年半続けて、このまま同じやり方で仕事していくことに限界を感じた。収入は原稿料のみ、典型的な労働集約型の仕事だった。勉強だと思ってどんな仕事でも受けてきたため、興味のあることばかり書いていたわけではなかったし、「書いて書いて書きまくる日々」にうんざりしてもいた。仕事を継続して回してくれていた出版社の担当者の異動とともに月の収入が急減したことで、仕事を主体的にコントロールできない立場であることを実感させられもした。また、原稿が掲載された媒体の仕上がりに不満が残るケースも少なくなかった。それで、編集まで自分で手がけたいと思うようにもなっていた。
仕事の方法を変えることを考え、アスキー3の求人広告を見つける。のちの『週刊アスキー』の前身にあたる週刊誌の立ち上げ準備に向けた募集で、週刊誌の経験を持っていた川越さんはすぐに採用された。
仕事のやり方を変えたいとは思っていたものの、出版業界自体を離れるつもりは毛頭なかった。
「どこかほかの業界に、という風にはならなかったですね。出版業界が好きだった。ここに居る人たちも好きだったし、業界の雰囲気そのものがやっぱり好きだったんでしょうね」
アスキーの正社員として入社、週刊誌立ち上げは川越さん在籍時には実現しなかったが、パソコンゲーム情報誌の老舗『ログイン』でニュースページのデスクを務めることになった。アスキーでの日々が3年を過ぎた頃、ロンドンのカルチャー誌『i-D(アイディー)』(1980年創刊)の日本版が創刊されるという情報を得る。

発信することの嬉しさと新鮮さ
『i-D』は、ロンドンのストリートカルチャーに着目した雑誌で、当時『Vogue(ヴォーグ)』英国版のディレクターを務めていたテリー・ジョーンズ氏4によって創刊された。さまざまな意味でのマイノリティに属する人々を通して既成の価値観を揺るがすことを期した雑誌で、世界のファッションやライフスタイルを牽引する存在になっていた。日本でも、都内の大型書店などで買うことができ、川越さんも読者のひとりだった。
その雑誌の日本版『i-D JAPAN』5の編集メンバーとして採用された川越さんは、編集のメインスタッフとして深く関わっていくことになる。LGBT、新興宗教家、少数民族、路上生活者……といった人々への取材を通した誌面構成を提案し、企画の多くが採用されていくなかで、川越さんはこれまで感じたことのない喜びを覚えるようになった。
「マイノリティへの思いは、もともと自分のなかにあったはずで、それが仕事になったことがまず嬉しかった。それから自分の企画がどんどん通る、やろうとしたことがかたちになっていくのは楽しかった。それまで依頼されたことを器用にこなしてきた自分にとって、自分がやろうと思ったものが次々に実現されていくのは新鮮なことだった」
1991(平成3)年にスタートした雑誌は日本でもコアなファンを獲得し、その影響力を発揮しながら刊を重ねたが、経営的には順調ではなかった。カウンターカルチャーの認知度がまだ低く、メインの広告主となるはずのストリートファッションの会社はいずれも歴史が浅かった。そのため広告獲得に常に苦戦を強いられ、16号で休刊を余儀なくされた。

漫画の神様の無念
『i-D JAPAN』の休刊後、『Esquire(エスクァイア)』の編集チームを経て、川越さんは雑誌創刊に再び携わることになった。角川書店から「雑誌100冊構想」が持ち上がり、そのうちの1冊の創刊メンバーとして召集されたのである。
雑誌(のちにムックとして刊行)は荒俣宏氏6の責任編集による『WONDER X(ワンダーエックス)』7というもので、同誌の第3号が、日本の作家・評論家といった知識人たちの「死」の周辺を描いた『知識人99人の死に方』という企画だった。荒俣氏がこの企画を通していちばん知りたかったのは、漫画家・手塚治虫が亡くなるまでのことだった。手塚治虫氏は、1989年2月に逝去した。死因は胃ガン。その病名は最期まで本人には告知されなかった。
「でも彼は医師でしょう。荒俣さんは、手塚さん本人のなかでも“グレー”だったはずだって言っていました。本当はガンだって分かってたと思うんだけど、それを信じたくない自分がいて、すごく苦しんだだろうって。壮絶だったはずだって。それを描き出してくれと頼まれました」
手塚治虫氏のページはこの本の象徴であり看板でもあった。こうして川越さんは「とにかく手塚さんのことで精一杯」の日々を過ごすことになる。
闘病のことをくわしく知るには、手塚夫人への取材が不可欠だった。死から5年近く経った時期で、まだ悲しみも喪失感も強く、承諾はなかなか得られなかった。ようやく許可された取材は手塚宅で行われ、手塚氏が複数の漫画を並行して書いていた仕事場の撮影も了承された。
書き上がった原稿は、99人が並ぶ目次の最初に掲載された。生涯で400作を超える作品を生んだ漫画家の殺人的な仕事量のこと、月に数回しか子どもたちに会えない日々のこと、周囲を心配させた深刻な睡眠不足のこと、病気発覚時ガンが全身に拡がっていたこと、そして臨終のこと——死の間際まで次にやりたい仕事を思い描き、一方でガンの疑惑に苛まれ続けた漫画家の無念を、川越さんの原稿は描き切った。

「売れる本」の手ごたえ
分野も仕事のスタイルも問わず、さまざまな媒体にそれぞれのかたちで関わるなかで、川越さんには、「読まれる本」「売れる本」を作り出していける手応えが生まれてきていた。世界の史実を新聞報道風に扱った『歴史新聞』8(80万部/日本文芸社)、歴史書『三国志』の『三国志新聞』(15万部/同)を手がけたことも大きかった。
さらに正社員として入社したアスペクトで川越さんは、事実上の出版社立ち上げを経験することになる。
「ある程度キャリアを重ねれば、雑誌の立ち上げや書籍編集部の立ち上げの経験などは順番に回ってくる。でも社員の立場で出版社立ち上げに関われる経験はそうないだろうと思って飛びついたんです」
川越さんはアスペクトの第一編集部(書籍専門)の編集長に就任し、木村伊兵衛賞を受賞した『ROADSIDE JAPAN珍日本紀行』(都築響一著)、『なつかしの給食』シリーズなどの編集に携わる。これらの本がヒットしたことで、「売れる本」に対する手応えは確信に変わっていった。「本を売る」ことに責任を持つ立場になり、さらにそこで好成績を重ね、版元としての立場に身を置くことの面白さは、川越さんを虜にした。書くことから作ることへ、作ることから売ることへ、本に関わる仕事の領域を広げてきた川越さんにとって、残るは「出版すること」だった。
「角川書店の仕事をしていた頃に、編集プロダクションの機能を持ちながら出版社になったという会社の人と会って、ああそういうこともできるんだなと思いました。ライターを始めた頃から、いつかは出版社を、と漠然とは思っていた。奥付の“発行人”のところに自分の名前が載ることをどこかでやりたいという気持ちが強まっていたんだと思います」
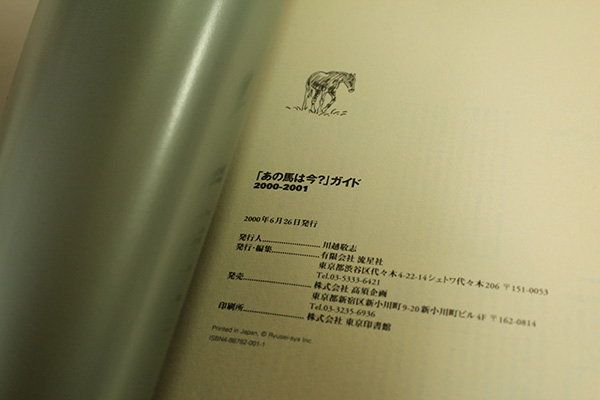
出版社「流星社」創立
1999(平成11)年4月、川越さんの会社「流星社」が誕生する。直近まで所属していたアスペクトから2人の社員を営業スタッフとして引き連れてのスタートだった。事務所は東京・渋谷区代々木のビルの一室に構えた。当初は編集プロダクションとして営業し、知り合いの出版社の取次口座を借りて、かつて活躍したサラブレッドの引退後にあったドラマを追った『「あの馬は今?」ガイド2000-2001』を発刊した。この本の販売実績が好調だったことを受けて、営業を任せていた浅見洋明氏が「この1冊と、アスペクト時代の実績を持っていけば口座は開けます。やってみましょう」と持ちかけ、流星社は取次各社との口座開設9の準備を開始する。
「当時のトーハンの担当者が高校時代の友達と知り合いで、『川越なら大丈夫だ』と口添えしてくれたそうです。他社との契約も、大変だったけれど浅見が活躍してくれました。僕は編集上がりで営業のことはあまり勉強していなかったし、出版社になれたのは浅見の功績。でも彼はいつも僕の作る本を信頼してくれて、『売るものがあるからできることです』と繰り返し言ってくれた」
川越さんは流星社の刊行分野を考える時に、「1位と2位は食っていける、3位はトントン。それ以下は難しい」という出版界のセオリーに基づき、トップに立てる分野を探した。アスペクト時代から競馬関係の本をいくつか扱っており、その分野に「(読者層が狭いため)大手が扱わない」「(編集力・営業力に優れた)競合が少ない」の2つの条件が揃っていることから、刊行分野として「サラブレッド」を選んだ。アスペクトで経験のあった「格闘技」と、少年時代からずっと好きな「サッカー」を加えた。いずれも実用書のカテゴリーに入り、書店の棚同士も近いため、書店担当者が同じというメリットもあった。
サラブレッドの顔にある白斑を「星」と言うが、そのうち鼻すじに沿って縦長に流れているものを「流星」と呼ぶ。サラブレッドを扱う出版社として、社名はそこからつけた。
競馬は賭け事としての面が目立つため、一部の熱心な競馬ファンを除いては、サラブレッドの生い立ちや個性を知ろうとしたり、馬主や調教師、騎手といったサラブレッドを取り巻く人々の生きざまに興味を持ったりする人は少ない。流星社の本を通して川越さんは、競馬というジャンルに対する人々の視野を広げ、新しい視点を提案したいと考えていた。
「当時この言葉は使われていなかったけれど、ブランディングを考えていたんだと思います。競馬のブランディングに貢献できる会社になろうと思った」
さまざまな媒体に関わることで培ってきた自身の本づくりによって、それを実現していった。
「それまで付き合ってきた写真家やデザイナーに恵まれたからできたこと」
と川越さんは話す。
サッカーの分野でも、作業の大部分を外注した格闘技でも、同じ考え方をもって作った本を出版していった。

再びの新しいフィールド
滑り出しが順調だった流星社は、しかし、創立から約1年後に大きな壁にぶつかった。代表である川越さんが病に倒れたのである。いわば流星社の「監督・4番・エース」であった川越さんが現場に出られなくなったことで、当初描いていた経営ビジョンは実質ストップすることになる。馬が好きで集まっていた若いスタッフは順に退社し、流星社は途中から運営に携わってきた奥さんの弘子さんと2人の会社になった。それから10数年、闘病にほぼ専念せざるを得ない時期が続いたが、良い医師に出会い、病気と付き合うことにも慣れてきた。
自らの取材・原稿・編集をもって本を作り、世の中に送り出したい。そうすることで物事への既成の概念に対する疑問を浮かび上がらせ、新しい視点を提供したい。それがすべての編集者の夢だとすれば、川越さんはさまざまなフィールドでその夢を1冊1冊に託し、出版業界を走り抜けてきた。
現在58歳。学生時代にライターとして業界に入り、徐々に仕事の領域を広げてきた川越さんは、「それでも自分のベースにはライティングがある」と考えている。2018(平成30)年現在、そのライティングの力をもって流星社はwebライティングなど新たな方面に向かっている。川越さんのライターとしての道のりが再び始まり、川越さんの前にまた新しいフィールドが広がっている。