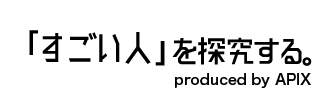“手づくりの素朴さ”へのこだわり
北京市中心の北側、かつては城壁だった安定門内大街の一本南寄りに、安定門と雍和宮のあいだを結ぶかたちで、幅約5m・全長約600mの細長い通りがある。「五道営胡同」と呼ばれる昔ながらの家並みが続くこのスポットが、近年静かな注目を集めている。
北京の人気胡同と言えば「南羅鼓巷」を思い浮かべる人も多いだろうが、こちらはいわゆる“お上りさん”をはじめとした内外の一般観光客でごった返す場所である。当初は“進取の気質”に富んだユニークで魅力的な店も少なくなかった。ところがその後、異常とも思える家賃の高騰などを背景にその多くが移転してしまい、いまでは観光客向けの定番的な土産店が集まっている印象が強い。
これに対して、五道営胡同は平日の日中の人通りはまばらで、集団で訪れる観光客はほとんど見かけない。おしゃれなBARやCAFÉ、雑貨店などが立ち並び、中間層を中心とした地元民やセンスの高い欧米人が楽しめる隠れ家的な空間となっている。
この五道営胡同の最西端、安定門側の門をくぐって数メートルの場所に、中国茶室「一拙」が現れる。2014(平成26)年、店主でオーナーでもある李染さんが、大学卒業後間もない25歳の時にオープンさせた店である。
店名の「一拙」は、「百巧不如一拙」(百の手の込んだもの〈=技〉はひとつの拙いものに及ばない)という思想家・老子の言葉に由来している。「一」はものごとの始まりを表し、純粋さと重なる。また、賢くない・つたないことを意味する「拙」は、修飾を最小限に抑えた素朴さをイメージしている。
「店名にも示されているように、この店では“大量生産品”ではなく、“手づくりの素朴さ”をお客様に提供しています。例えば、喫茶に用いる器をつくる場合にも、人間の肌に合ったものづくりを重視します。店のロゴについても、“手のひらとサボテン”を組み合わせて『拙』を表現することで、コンセプトが一目でわかるようにしているのです」

お茶を先進的な飲み物に
李さんは、なぜ中国茶室を開こうと思ったのか──。
「お茶は中国の伝統的な素晴らしい文化であり、とても多くの魅力あるものです。ところが、いまの若者たちはあまりお茶に興味を示さなくなってきています。彼(女)らのお茶に対する既成イメージを打ち破りたい。それがそもそもの動機でした」
中国は17、18世紀において世界の茶市場を独占し、生産・輸出のどちらも絶対的な地位を築いていた。19世紀に清朝が列強の侵略を受け、半植民地化されるに従って、中国はその優位を失うと同時に、茶文化そのものも衰退していく。さらに日中戦争などを経るなか、中国人は100年以上にわたって苦難を余儀なくされ、日常生活における喫茶の習慣は中断した。とくに文化大革命(1966~76)期には、資産階級(=ブルジョアジー)の享楽行為とみなされ、茶館は取り締まりの対象になった。この頃の中国人は日常、白湯を飲んでいたと言われる。
「日本へ行ってみて感じたのは、自国の良き伝統文化がきちんと継承されていることでした。例えば、花火大会における浴衣姿などもそのひとつです。中国ではいま、伝統文化を重んじる精神を日本から学ぼうとしている人が少なくありません」
とくに1980~90年代生まれの若い世代が、外国のさまざまなものを実際に目にするようになってから、伝統的な文化を大切にする機運が強まりつつある。
中国では改革開放以降、茶文化の復興が謳われ、喫茶の習慣も広く浸透していった1。その一方で近年、人々の生活水準が向上するに従って、飲料の多様化が急速に進んだ結果、若者たちのあいだでは、お茶は一種時代遅れ的な感覚を持つ古い飲み物という評価も広がっている。
「『一拙』には、そうしたお茶に関心を持たなくなった若者たちを対象としつつ、年配者を中心とした喫茶の習慣を好む人たちにも集まってもらえればいいなあ、と思っています。若者たちには興味を惹くアイデアに溢れた斬新なオリジナルのお茶を、年配者たちにはより質の高いお茶を最高の状態で提供しようと考えました」

店づくりのキーワードは「古風」と「素朴」
大学でデザイン学を専攻した李さんは、2012(平成24)年頃から「一拙」の開店に向けた準備を具体化させる。まず場所選びである。
「胡同の中であることは絶対条件でした。胡同は北京の象徴であり、一家団欒の温かいイメージがあるからです」
李さんは1989年生まれであるが、1980~90年代におけるアットホームな雰囲気の家に対する郷愁の気持ちが強かった。改革開放以降、北京ではマンションや高層ビルの建設ラッシュが続き、さらに2008年の北京五輪は大規模な再開発工事を加速させ、ほとんどの観光向け以外の胡同は取り壊されていった。
納得できる場所を見つけるべく奔走した末、五道営胡同の現店舗となる建物と巡り合う。200年余の歴史がある民家だった。このため、まず店に相応しい外観にするとともに、開店に向けた改装工事に取り組むことになる。
「外観は白塗りの壁を基調として、店内を覗ける2つのガラス張りの窓を付けました。そして、白壁にシンプルなロゴを配し、間接照明が当たるようにした。また、屋根は四川省出身の職人に依頼して、竹の葉で編んだ莚(むしろ)を使いました。その結果、店の外観に、白とグレーの美しいコントラストが生まれました。内装は、もともとあった古い梁柱と構造をできるだけ活かすように工夫しました。数十年の歴史がある照明器具をはじめ、山西の戸棚、上海のソファーといったように、家具等はすべて各地からアンティークを取り寄せています」
「一拙」の内装は1980年代を懐かしむ装飾を基本としており、古風と素朴を特徴とした。店内のすべては、それぞれが本来持っている特質を活かすことに力点が置かれ、最新流行でもなければ、特別なヴィンテージでもない。こうしたセンスは、美に対する関心が高く、本物への興味が強く、ものづくりに対するこだわりをもつ李さんならではのものだった。
また、店の入口に至るまでにわざわざ回路(白いコンクリートによる4、5段の階段)を設け、お客様がそこを経ることで、気持ちを落ち着かせることができるような配慮も加えた。
開店資金に関しては、2つの方法をとった。ひとつは若者の起業家を対象とした国からの支援策の活用である。ローンを組んでも、最初の3年間の利息はゼロとしてもらえた。もうひとつは実家からの借金であるが、いずれもいまはすべて返済しているという。
「若者が自分の店を経営することは、いまの中国では決して珍しくありません。私のまわりにも、カフェや民宿、古着屋を経営する者が何人かいますよ。大手企業に就職して組織の歯車として働くよりも、自分の生き方を実践したいと考えている人は少なくないのです」

最高質の茶葉と手づくりの器
李さんは13歳の時、内モンゴルを一人で旅した経験をもつ。生まれ育った河北省邯鄲市から列車を乗り継ぎ、最後は馬に乗って現地を巡ったという。一人っ子が原則の中国ではとても珍しいケースであり、ほとんどの親は子どもに対して過保護な振る舞いをするのが普通だった。
「両親は共働きで忙しく、子どもにかまう余裕もなかったのでしょう。もちろん、教育方針として、あまり干渉せず、本人の意思を尊重する、という考えもありました」
「一拙」の開店を見据えて、かねてからの趣味であった旅がより加速する。旅先は国内にとどまらず、日本や台湾、韓国、インド、ネパールなどにまで広がった。そして、この圧倒的な行動力により、自分が納得できる最高質の茶葉の確保に成功する。そのひとつが、台湾の梨山2においてある茶農家と巡り合ったことである。
「人知れぬ場所で茶園を経営されている方と出会えました。そこは自然栽培に徹しており、オーガニックなお茶が栽培されていたのです。野生特有の甘味が強く、既存のお茶では味わえないとても豊かな風味がありました。産量は少なくきわめて希少性が高いもので、さっそく契約を結ばせてもらいました」
一方、喫茶に使う器についてもこだわった。それぞれに特徴のあるお茶は、それぞれに適した器を使うことで、より一層味わいが深まる。このため、まずデザイナー探しに奔走した。
「当初は、日本や台湾、北欧の職人さんとの連携に力を入れました。デザインそのものだけでなく、お茶の特徴などさまざまな情報を店側から提供するように心がけました。一方で、ネット等で見て良いと感じた外国のデザイナーや、その作品に関する情報を、中国のデザイナーに伝えるように努めました。中国には伝統的に器へのこだわりが強い文化があり、時間がかかってもそれを復興すべきだと考えたのです」
デザイナーの中には陶芸専攻で技術を学んできた人もいるが、大半はデザイン学を学んだ人たちで、センスを育むことができる環境が大切という。
「一拙」で扱われる器のデザインは、鮮やかな色を使うのではなく、モノトーン(白黒)やベージュなど長時間にわたって飽きのこない点が特徴といえる。
「白色を重視している理由は、最も好まれる色だからです。でも、同じ『白』と言っても、さまざまな色があります。例えば、温かみのある白、真珠のような深みがある白、少し明るめの白、というように、異なるニュアンスの器を揃えています」

伝統にとらわれない斬新なメニュー
「一拙」の店内は2つの部分に分かれる。入口すぐのスペースは喫茶に使う器のセレクトショップであり、その奥に喫茶スペース(=茶室)が広がる。セレクトショップでは、喫茶に関する道具、デザイナーによる手づくりの器などが陳列販売されており、鑑賞するだけでも楽しい。そして茶室では、展示されていた器を実際に使ってお茶を楽しむことができる。
「デザイナーが思いを込めた器を実際に使うことを通じて、お茶に興味を持ってもらうきっかけになれば、と考えています。良いお茶は自然と適切な器を要します。自分の好きな器を使うことで、お茶の香りをより濃厚に感じられます」
メニューを見ると、一拙オリジナルのフレーバー茶(=風味茶)、厳選された産地から取り寄せた紅茶や烏龍茶、プーアール茶(普洱茶)がそれぞれ数種類ずつ取り上げられている。
李さんにとくにお薦めのお茶を尋ねると、夏限定の「香槟烏龍(Champagne Oolong)」と冬限定の「炎紅茶(Fire Brandy Black tea)」の2つの名前が挙がった。
「香槟烏龍は20時間かけて水から淹れた冷たい烏龍茶です。アルコールは入っていませんが、シャンパンのような細かい泡の触感が楽しめ、口の中に清涼感が広がります。炎紅茶は、ブランデーをほんの少し加えた紅茶で、飲むとすぐに身体が温かくなってきます。ナポレオンが珈琲にブランデーを混ぜて飲むのを好んでいたことをヒントに、ブランデーと安徽省祁門県3を産地とする紅茶を組み合わせたものです」
この店では点心(=茶菓子)も充実している。メニューのひとつである「小仙桃」は、伝統的な米と小麦粉を素材に蒸して完成させる。中に入っている餡は甘酸っぱいイチゴ味で、さわやかな味わいが口いっぱいに広がる。
「これは伝統的な中国の点心です。中国では桃はとても縁起のいいもの(=長寿の象徴)で、多くの人から好まれています。点心もまた、それぞれのお茶に合わせて、菓子職人と相談しながら開発しています。当初は日本の職人の協力も仰いでいるんですよ」
お客様には1970年代あるいは80年代以降の生まれの人たちが圧倒的に多い。自由業やメディアに従事する人、さらに美食家や観光客など、その肩書はバラエティに富んでいる。
「一拙」の店内では、李さんがこうしたお客様と、お茶はもとより、旅行やカメラ(写真)、グルメなどの話題について楽しそうに語り合っているシーンをよく目にする。来店するお客様とすぐに仲良くなるのである。そして、“友人”はまた新しい“友人”を連れて来る。
本格的な喫茶の経験をもたない多くの人が、「一拙」にやって来て、ゆったりとした空間のなかで、本物のお茶を楽しむことによって、その魅力を再認識していく。