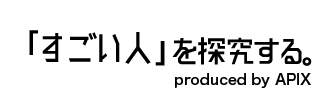「仲間」が集うような店を
酒庵「ウタリ」は、いまから半世紀以上前の1960(昭和35)年、現店主である井口和夫さんの母上・利子さんが、北海道札幌から単身上京して西池袋の地に開いた。現在入居している福住ビルが建設される前で、同じ敷地内に建つ木造2階建の1階を借りての出店であった。
当時の池袋駅西口から北口にかけては、まだ闇市の名残1が色濃く、治安こそ悪かったものの、大きな繁華街が形成されていた。とはいえビルの姿はほとんどみられず、東武東上線池袋駅(西口)に東武百貨店がオープンするのは、「ウタリ」開店の2年後のことである。
店頭には現在と同様、墨字で「ウタリ」と書かれた和紙行燈と暖簾が掲げられる。店名は利子さんが考えたもので、アイヌ語で「仲間」「友だち」を意味する。北海道にある民家のような落ち着いた空間の中で、誰もが分け隔てなく、笑顔で酒を飲み交わすことができる場所──この名前に込められた思いこそが、酒場としての理想的な姿を明確に示している。
店に入ると、10名ほどがゆったりと座れる奥行90㎝ほどはあるL字の立派な一枚板のカウンター。その中央に年季の入った炉(囲炉裏)が構え、奥に調理する小さなスペースがある。カウンターの左端には、いつも季節の花々が飾られる。また、手づくり硝子工房の老舗・北一硝子(小樽)で購入したガラス玉照明をはじめ、アイヌの民族衣装をあしらった版画、鮭をモチーフとした絵画など、店のそこかしこに北海道らしさがみられる。鳩の形をした民芸酒器である鳩燗徳利も、この店の特徴のひとつである。北海道ではよくみかけられたもので、囲炉裏の灰に刺して温めると、遠赤外線効果でまろやかな味になるため、燗酒好きの常連客から絶大の支持を得た。
当初は手の込んだ料理をほとんど出しておらず、新鮮な魚介類や旬の野菜を炭火でじっくりと焼いて提供するメニューがメインであった。囲炉裏酒場というスタイルは、札幌や旭川などでは珍しくなかったものの、東京ではまだほとんどみられなかった。流通がいまのように発達していない時代にあって、「北海道の新鮮な魚介類」を出す店も少なかった。とにかく質の良い「本物」を味わってもらいたい──この姿勢は当初より現在に至るまで「ウタリ」に貫かれている姿勢で、素材の質には徹底してこだわった。
西池袋の界隈は当時、“怖い場所”というイメージが強く、サラリーマンを寄せ付けないような街だった。そのなかで「ウタリ」のお客様は、立教大学の教授など教育関係者や出版関係者のほか、池袋という土地柄もあって漫画家2も少なからずおり、個性的な人たちが常連客となっていった。

名店での厳しい修業を経て
のちに2代目店主となる井口和夫さんは、1948(昭和23)年9月、北海道札幌で3人兄弟の末っ子として生まれ、地元の中学校を卒業して高校入学の時に上京する。さらに高校卒業後、日本料理の修業へ出る。
「子どもの頃から料理を作ることは嫌いじゃあなかったからね。12歳の時におふくろが上京したこともあり、家族のために料理を作る機会は少なくなかったけど、2人の兄貴たちよりも料理はずっと上手かったよ」
静岡県伊豆市で「師」と呼べる親方と出会い、湯ヶ島温泉にあった「落合楼」3という老舗高級ホテルで修業を積むことになる。
落合楼では、料理の素材は親方の指定のもと、すべて東京で一括するかたちで仕入れられ、築地から10時頃着のトラックで運ばれた。300人ほどの宿泊客に朝食を提供したのち、届いた食材の仕込みが始まる。13時から2時間ほどの休憩をはさみ、夜の食事の準備に追われる。井口さんは厳しい毎日のなかで、仕込みと鍋を洗う日々が1年以上続いたという。
当時の料理の世界はまだまだ前近代的な職場で、年齢を問わず先に入った“先輩”が絶対的な存在だった。イライラした“先輩”から茶碗や鍋が飛んでくるなど、理不尽なことも日常茶飯事であった。井口さんも、「入った道を誤ったかな」と悩んだ時期もあったという。それでも、生来の真面目な性格に加え、良き師に恵まれたことが、腐ることなく修業に励む背中を押した。
「親方はとても真面目な方で、お酒も飲まなかったけど、料理の腕は一流だった。目利きも含めてすべてをひっくるめて腕が良かったし、几帳面な方だったからね。いろいろなことを教わることができたよ。何も知らずに入った世界では最初が肝心。その意味で運が良かったよね」
5年間に及ぶ修業を終えると、東京の日本料理店で店を任される。5人ほどの後輩の面倒をみながら店を仕切る毎日が続く。そんななか、利子さんのパートナーとして開店以来「ウタリ」を手伝っていた女性が店を辞めることになる。
「店を継ぐ考えはそれまでなかった。だけど、この時初めて手伝ってみたいと思ったんだよね」
そして、強い慰留を受けながらも、「ウタリ」へ移る決断をすることになる。井口さんが24歳の時のことだった。
「ウタリ」では、修業時代に身につけた調理の技はあえて封印したという。素材の良さをできるだけ活かすため、あまり加工しないことに気をつけたからである。とはいえ、修業を積んだプロの板前が店に入った結果、メニューは格段に広がった。刺身や鍋料理のほか、炭火焼きにも黒毛和牛串焼きや徳島阿波尾鶏焼鳥などが新たに加わった。
1979年11月には福住ビルが竣工し、同ビル2階(現在地)へと移転する。新しい店はほぼ最初の店と同じかたちとしたが、店の隣に新設された「ウタリ専用室」(トイレ)が大きな変化であった。
「女性のお客様が多かったこともあって、あからさまにトイレに行くことがわからないように、ちょっと外へ出るかたちでトイレに行けるように配慮した。おふくろのアイデアだよね」
その後、井口さんの奥様である現女将・節枝さん(長崎・五島出身)が本格的に店を手伝い始め、利子さんと3人で店を切り盛りすることになる。そして約半年後、利子さんは現役を引退する。まだ60歳という若さであった。
「おふくろはわれわれ夫婦を気づかって、そろそろバトンタッチしたほうがいいと思ったんだろうね。店が狭いので、3人で店に立ったのは短いあいだだった」

良い素材さえ出せば、美味しくなる
「ウタリ」で井口さんがこだわってきたことは、まず何よりも素材であった。自分の目で確かめて仕入れるのは、基本中の基本である。このため、毎朝5時に起きて築地市場へ通う毎日が続く。
「同じものでも産地によって、また時期や年によってまったく違う。だから、機械的にこの産地ならOKっていうんじゃ駄目。その時々にいちばん良い素材を厳選しないとね。築地で満足なものを仕入れられないものは、産地から直送してもらっている」
店の看板商品である本柳葉魚(ホンシシャモ)4については、とりわけこだわりが強い。
「『日本一』を謳っているだけに変なものは仕入れられないからなぁ。きょう良いものが入っても、明日も入る保証はない。お客様の期待が大きいだけに、『日本一』の看板は譲れないね。目に叶うものが手に入らなければ、無理して店に出さないよ」
「ウタリ」では食感の楽しさも重視しているため、子持ちの本柳葉魚しか仕入れない。味だけを考えれば栄養価の高い雄のほうが美味いと言う人もいるが、どうしても卵の食感を大切にしたいという。
「そこは大きなこだわりのひとつだね。卵の腹の持ち具合がいちばんの目利きのポイントになる。あと、完熟しているか未熟かは見ればすぐにわかる。ただね、絶対数が少ないから、どうしても最高の本柳葉魚を確保するのは難しくなってきているよ」
日本ならではの「旬」を楽しんでもらうことにも力を注ぐ。「茶豆」「時鮭(時しらず)」「千住(寿)葱」などは、その代表と言える。
秋鮭(秋に捕れる鮭)は川に入ったら産卵に向けて捕食しなくなるため、徐々に味が落ちていくのに対し、春から初夏にかけて北海道付近からオホーツク海近くで捕れる時鮭は、脂がのって格段に美味しい。また、主に東京・足立区(千住)で収穫される江戸野菜のひとつである千住葱は、約200年前から食通をうならせてきた“極上の葱”で、一流料亭がこぞって使う。旬の時期は短いが、甘さ・辛さ・うまさ・太さ・食感の5拍子がそろった究極の長葱と言われている。
「料理なんてそんなに難しいものじゃなくて、その時々の最高の素材を最大限に活かせば美味くなる。『枝豆』や『あん肝』など、時期でないものを無理に出すから、冷凍品やまがい物5を使うことになっちゃう。なんでも一年中食べられると思っている人も多いけど、それが偽物であることを知らないんだよ。日本人が本来大切にしてきた季節感、旬の食という楽しみがおかしくなってきちゃっているよね。『ウタリ』では、そこはとことん大切にしたい」
こうした「旬」の素材を活かしたお通しも、「ウタリ」のこだわりの逸品である。
「食べ歩きなどをしていて痛感するのは、お通しがしっかりしている店は、どんなものを頼んでも間違いがない、ってこと。最初に出てきたお通しですべてが決まっちゃう。だからこそ、お通しには力を入れているし、そこで期待感を持ってもらえれば嬉しいね」
ある日のお通しは「蒸した毛ガニ」と「本マグロの山かけ」だったり、「ヤリイカと葱のぬた」と「子持ち昆布のおひたし」だったりする。常連客の中には、お通しだけで酒を何杯も飲んで帰る人も少なくない。「日本一贅沢なお通し」と言っても過言ではない。
一方で飲み物は、日本酒の「高清水」(以前は「新政」)、焼酎の「吉四六(麦)」「一刻者(芋)」など、厳選されたものしか扱わない。グラスやジョッキはすべてほどよく冷やされ、氷も専門店から毎日取り寄せる「純氷」を、使う直前に一つひとつ砕いてから出す。
「製氷機の氷だとすぐに解けちゃうし、第一にまずいからね。せっかくならば美味しい酒を飲んでほしいじゃない。大きな純氷を砕いて使えば、大きさも形も違ってとてもいい味が加わる。どうってことない手間なんだけどね」

目の届くところにお客様がいる
移り変わりの激しい飲食業界にあって46年間、開店から数えれば58年間も「ウタリ」が続いている背景には、素材や旬へのこだわりのほかにも理由がある。それはお客様一人ひとりへの心配りである。
「自分の身の丈を振り返ってみれば、いまの店は規模的にもちょうどよかったなぁと思う。お客様一人ひとりの顔を見て、接客することができるし、注文への対応も無理なくできるからね。座敷をつくると話すこともできなくなっちゃう。お客様の顔が見えるというのは、やっていてとても楽しいよ。反応もよくわかるしね」
かつて同じ福住ビルで商売をやっていた仲間の多くは、バブル期に手を広げていってみな失敗していったという。
「当時は銀行が低利でどんどん融資したからね。元の規模でやっていればなんてことなかったのに、手広くやろうとすれば味は落ちるし、元の店までなくしちゃうことになる。食べ歩きの経験から良い店に共通していたのは、お客様のことを第一に思ってやる姿勢だった。料理にしても接客にしても、それがさりげなくできている店がとってもいいなぁ、と感じた。いまは少なくなっちゃったけどね」
「ウタリ」では、お客様の肩書きはすべて外される。お客様はみな同じ立場・同じ条件というのが、居心地の良さの要因のひとつでもある。また、店が雑居ビル2階の一番奥というわかりにくい場所にあるため、お客様が新しいお客様を連れて来て、常連客が増えていくケースが少なくない。いわば意図せぬ「会員制」のようなところがあり、そうした積み重ねによって、店の雰囲気が創られ、高いレベルで保たれてきている。
店内にはBGMなど余計な音が一切ないのも、この店の特徴と言える。静かで落ち着いた空間のなかで、お客様の声が心地良く響き合う。
「カウンターだけなので、たまたま隣りに座ればお客様同志でいろいろとお話をしてくれる。『ウタリ=仲間』という店の理想が実践できたと感じる時だね。常連のお客様が店の良い雰囲気を醸し出してくれているんだ」
一方で、「ウタリ」は、利子さんの代から現在に至るまで、若いお客様に酒場でのマナーなどを教える場でもあった。目上の者が目下の者を連れて来て、本物の美味しさを教えてあげる。若者たちは店に通うなかで、酒の飲み方や料理の食べ方を教わって大人の社会人へと成長していった。また、年配の常連客が若いお客様をみて、「ビールを何本か出してやってくれ」と振る舞う光景も少なからずみられた。そうした何気ないやり取りが積み重なることにより、良き伝統が築かれてきた。
「『ウタリ』で長年やってきて得られた財産は、なんといっても『人』だね。いろいろなお客様と出会い、いろいろな話を交わすことができたよ。毎日店を開けるのが楽しくてね。きょうはどんなお客様が来てくれるかな、と思うとわくわくしてくる。久しぶりに顔を見せてくれるお客様も嬉しんだよなあ。ただねぇ、長年やっているとどうしてもお客様が亡くなったりする。これは本当に辛いことだね」
井口さんには3人の娘さんがいるが、後継候補は見当たらない。58年間続く「ウタリ」は、井口さんが“最後の大将”になりそうである。
「まあ、こればっかりは仕方ないからね。でも、まだまだ身体が続く限りはやり続けたいと思っているよ」
優しいまなざしで前を見据えるその姿は、去年9月に古希を迎えたとは思えないほどエネルギッシュだった。